嶋瀬氏:日本では今後、ノンクレジットの広告記事を掲載するメディア、またその手法が自然淘汰されていくだろう。やはり、ユーザーの信頼を裏切ってしまうサービスからは、どうしてもユーザーは離れていく。ユーザーを含めた監視の目が非常に強くなってきているなか、企業や媒体としてのレピュテーションリスク(評判・風評リスク)も高い。
コンテンツを見て「これはおかしい」となると、それを出稿している企業、掲載しているメディア、それを配信したプラットフォームのすべてが不利益を被る。結局、最終的なステークホルダーであるユーザーを見ている企業しか生き残らない。それは自然な流れだと思う。
自然淘汰のプロセスを早めるうえでは、JIAAや我々を含めて、この分野で経験のある企業や団体が、有効な施策をともに考えていくことも当然重要だ。
泊氏:米国では、Interactive Advertising Bureau(IAB)がオンライン広告の技術的標準規格を策定しているほか、広告審査などを行うNational Advertising Division(NAD)が、広告表記に関して業界内に自主規制を促している。
日本ではまだ事例がないが、海外では、「ハンバーガーの新商品を消費者に食べてもらって、その感想を消費者自身に書いてもらった記事を広告として拡散したい」というような広告主側からのリクエストがある。
米国ではクレジット表記が徹底されているため、「無料で提供されたクーポンを使って商品を購入し、記事を書いた」といったクレジットを入れている。つまり、「ある企業に招待されて食べた意見」といったことを記事に明示している。企業もそこを隠しておらず、逆に明示することによって信頼性が高まり、ユーザーに読んでもらえるような状況だ。
――海外でのネイティブ広告全体の状況は。
嶋瀬氏:米国では、企業とのタイアップ記事は年間で何本しか出さないと明確にうたったり、広告クレジット表記を徹底しているというのが、少なくとも我々がお付き合いしているメディアに関しての印象。
現在、オウンドメディアを格納するメディアが増えてきている。たとえば我々は、英国The Guardian(ガーディアン)のサイトの中に、アウトブレインのパートナーサイトといった形で、ガーディアンの記者がアウトブレインに関連するような記事を書いてもらうメディアを持っている。スポンサーがアウトブレインであることは、サイト上や記事、URL(http://www.theguardian.com/media-network-outbrain-partner-zone)などすべてに明示している。
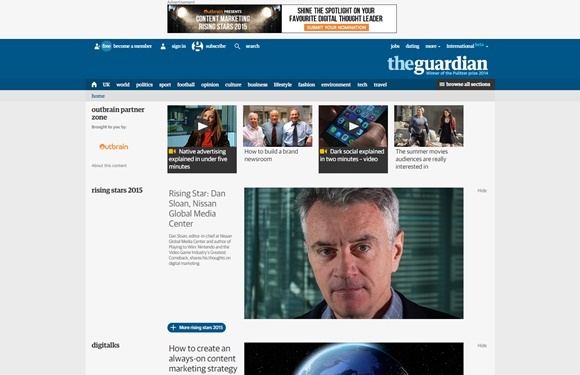
最終的に我々が求めているのは、そのオウンドメディアを通して、コンテンツマーケティングを多くの人に知ってもらったり、そこにアウトブレインを関連付けてもらったりすることだ。
――Outbrainではネイティブ広告の配信時、具体的にどのような対応をしているか。
泊氏:独自のガイドラインに則ってコンテンツの審査をしている。たとえばコンテンツとして配信するものが“広告的なランディングページ”ではないかなどをチェックする。コンテンツとしてみなされないものについては、お断りしたり、改善案をお伝えしたりしている。
嶋瀬氏:ガイドラインにはさまざまな項目があるが、すべてに共通する要素が2つある。1つは「ユーザーの“読み物モード”を阻害しないかどうか」。もう1つが「ユーザーにとって商品やサービスを超える有益な情報性があるか」。
具体的には、教養的な内容やハウツーのような実用的な内容があったりだとか、我々が“インスピレーション”と呼ぶ、それを読んでなにかひらめきや感動を与えられるかなどをチェックする。それらに当てはまらないコンテンツは掲載しないようにしている。商品やサービスのコンテンツが含まれることがいけないとは決して思っていない。ユーザーにとって有益なかたちでその情報を届けることが重要だ。
我々のサービスの強みは「マッチング」。どのような情報であっても、興味のない人に当ててしまうと、それは有益でない情報になってしまう。まずは我々のレコメンデーションエンジン上で、最大限、興味や関心の合うユーザーの軸をレコメンドさせていただく。これによって、最初に情報の価値を高めている。
また、コンテンツの入口となるタイトル、サムネイルなどで、ユーザーが今から自分がどこに飛んでいくのか、飛んだ先のコンテンツはどういった企業やメディアが作っているものなのか」を明確にわかるようにしている。
――ガイドラインを通らないコンテンツは多いのか。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する