企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が推進される中、ドラッグストア業界はDXにやや遅れをとっている印象がある。アプリ導入やDXの状況など、元ココカラファインでデジタル推進を担当し、現在は店舗のICT活用研究所代表である郡司昇氏に話を聞いた。聞き手はランチェスター プランナーの篠田健吾氏。

ドラッグストアはポイントカードや会員カードをつくる際の情報登録が紙ベースであったり、登録不要ですぐに使えるパターンが多く見受けられ、個人情報などのデータ活用に遅れをとっている印象があるが、実際はどうなのだろうか。
もともとDM(ダイレクトメール)を送るために申込書に住所や名前を書いてもらっていたが、現在ではDMを送るドラッグストアは少なくなっているという。そのため、そもそも個人情報を聞かなかったり、申込書を書いてもらってもそこからデータにしていない企業もあるという。
データを活用できていないということは、つまり、顧客データを管理するCRMの導入に課題がありそうだ。CRMを導入しているのは大手数社ぐらいとのことで、まだまだCRMを導入している企業は少ないという。なぜ、導入が進まないのだろうか。
ドラッグストア業界では新しいものの導入に対して腰が引けている部分があると郡司氏は言う。とはいえ、マーケティングや販売の担当者には「新しい取り組みをしなければ」と思っている人も多く、アプリ導入などのチャレンジはしているものの、データ活用には至っていないという。
CRMについては、システム云々ではなく顧客視点が必要と郡司氏は言う。しかし、顧客軸のデータマーケティングができている企業は少ないと感じているそうだ。CRMを導入している大手数社でも、データを活用して何をしているかというと、顧客一人ひとりの分析ではなく、商品軸での分析をしているという。つまり、「この商品が売れているからチラシに掲載しよう」と販促のために使っているということだ。
顧客軸ではなく商品軸ばかりに目を向けてしまうと、地域や店舗に合わせた効果的な打ち手を出せないという問題に直面する。よくある失敗例として、M&Aで全国チェーンになって東京に本部ができた場合、そこで一括で商談をしようとする。本当は、各エリアで売っているものも、売れるものも違うため、本部だけで話を進めてしまうとうまくいかなくなってしまう。
たとえば、関西のドラッグストアではPVA洗濯のりがたくさん並んでおり、関西の人にとってはそれが当たり前だが、関東ではあまり見かけない。全国展開しているドラッグストアが抱える課題として、こうした地域や店舗の特性によって品揃えやレイアウトが異なることを把握できていないということもあるそうだ。全国で同じような施策を打っても、売れるはずのものが売れなくなってしまう。地域特性を把握し、マーケットに合わせた打ち手が必要なのだ。
一方で、CRMを導入し、売上アップにつなげているドラッグストアもある。全国チェーンのA社と地方チェーンのB社では、店頭に端末があり、ポイントカードかアプリのバーコードをかざすと、クーポンが表示される。画面の下タブに、薬、化粧品、ペット用品などのカテゴリが表示されており、その中から自分がほしいクーポンを選ぶ。何度か買い物をしていると、過去に選ばなかったタブが消えていき、よく選ぶタブのカテゴリは中分類にブレイクダウンして、より細かいカテゴリを表示するという仕組みだ。
たとえば、化粧品を選んだ人がいたとして、何度か選んだあとに、もう一段階細かいカテゴリの、基礎化粧品と色物コスメの選択肢が出る。そこからさらに、色物コスメをよく選んでいたら、口紅とチークから選ばせる……といった感じでその人がよく買っているものを深掘りしていく。そうしてパーソナライズされたクーポンや割引情報を表示することで、顧客単価が上がり、売上にもつながるといった具合だ。
ドラッグストアでは、LINEやチラシなどで5%オフ、10%オフクーポンをよく配信している。たとえば、LINEであればクーポンを配ることでLINE公式アカウントの友だちは増えるが、ペイできていないのではと郡司氏は指摘する。
ドラッグストアは粗利益率が低い業界であり、営業利益率は5%前後のため、クーポンで全品10%引きは身を削る販促であり、また、配信する人数によって費用がかかるため、赤字になってしまうという。また、紙のチラシについても費用対効果としては赤字だという。
ドラッグストアは紙のチラシを重要視している傾向があり、「チラシが命」という店舗もある。経営サイドとしては経費削減したいという意向はあるものの、チラシが多いほうが売上は上がり、また、競合他店がやっているとやめられない。そうして長年のあいだチラシ合戦になっているという。
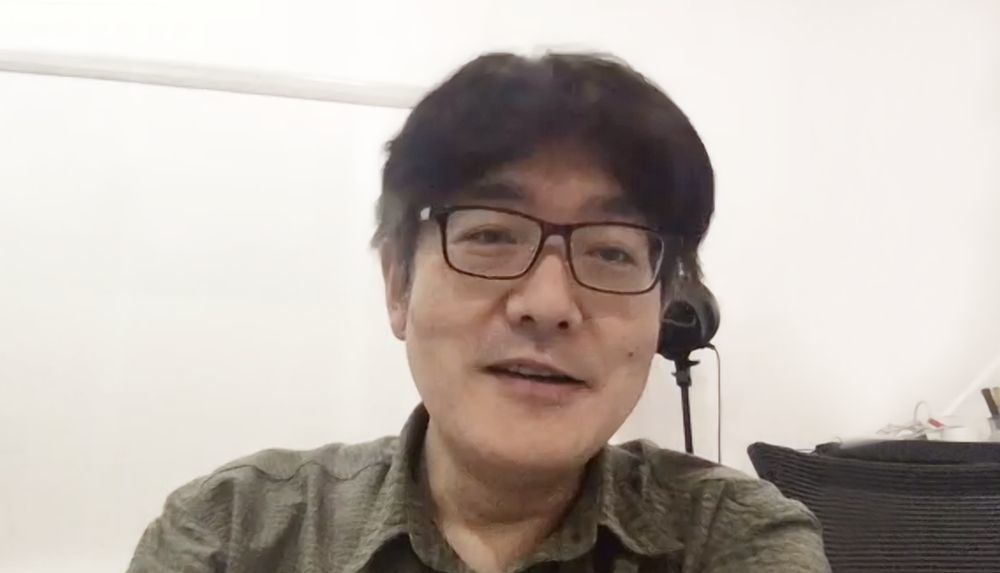
郡司氏が在籍中にココカラファインで作ったアプリでは、登録した店舗のチラシや販促カレンダーを閲覧できるようにした。特に、車で移動する郊外立地の店舗では効果的であったそうだ。アプリなら配信数の制限がなく、費用が抑えられメリットが大きいという。クーポンやチラシにおいても、全員にばらまくのではなく、顧客に合わせたクーポンを出せればチラシ・クーポン合戦からも脱却できるのではないだろうか。
ドラッグストア業界では、ECは積極的に展開しているイメージがないが、実際はどうなのだろうか。郡司氏によると、ドラッグストア業界は、実は商品点単価と粗利益率が低い業界でECに不向きだという。
ドラッグストアのECで需要があるものは、水やトイレットペーパーなどの大きいもの・重いものが多く、そうなると、配送コストばかりがかかってしまう。そのため、ECで大きな利益を上げるのは厳しいという。黒字化するだけでもそう簡単な話ではない。一方で、店舗受け取りサービスを行っている店舗では、その店の棚になくても、チェーン他店の商品を取り寄せできるなど、評判は良いという。店舗受け取りや在庫情報を知るサービスはニーズがあるようだ。
最近のEC業界では、コロナ禍で外出自粛が続くことで、ライブコマースやZoomなどオンライン接客などを試す店も増加しており、新しい接客スタイルが注目を集めているが、ドラッグストアがオンライン接客をすることについて郡司氏は肯定的だ。また、顧客分析ができれば、個人に合わせた接客ができるようになり、外出がはばかられる今、アプリで接客するのもアリだと郡司氏はいう。
このほか、SNSやオンライン配信ツールを活用してオンラン接客を試す店舗も増えている。ただ、いたずらにチャネルが増えてしまっては、管理が行き届かないという懸念も出てくる。チャネルを増やすのではなくアプリに統合すれば、店頭に近い接客ができるかもしれない。
顧客分析ができていれば、顧客の購入履歴が分かり、店員は「最近美容液を買ったばかりだからまだいらないだろう」「美容液の上に塗れる日焼け止めを勧めてみよう」など、どう接客すべきか予想が立てられる。顧客にとっては、自分のことを分かってくれている店員にならまた相談したくなり、店側にとっては、人件費の最適化にもなる。
実際、化粧品担当者が店内にいても、ずっと接客をしているわけではない。そこで、特に優れた化粧品担当者をオンライン接客担当として、自宅などから接客できる状態にする。店頭にタブレットを置いてアプリで接客できるようになれば、その人は全ての勤務時間を接客にあてることができ、勤務時間が短い分、時給を上げるなどすれば、担当者のモチベーションも高まる。
そして、化粧品の接客頻度が高くないなどの理由で、化粧品に詳しい担当者がいない店舗でも、満足のいく接客を提供することができる。そうすることで、トータルの人件費が削減されて、売上アップにもつなげられるのではないだろうか。
今回の郡司氏のお話を聞くと、ドラッグストア業界のDX推進には”顧客軸のデータマーケティング”が鍵を握っているようだ。まずはCRMを導入し、顧客分析をすることで、顧客に合わせた接客が可能になる。それが結果として、顧客単価を上げる取り組みにもつながる。
オンライン接客についても、まずは顧客分析ができていることが重要だ。ライブコマース、オンライン接客など、手法はさまざまあるが、ただチャネルを増やすのではなく、顧客情報を統合して管理できているか、ということが重要だ。アプリを導入するのであれば、こうしたチャネルを統合し、CRM連携を想定したコンセプトメイクを行う必要があるだろう。
(郡司氏とプランナー篠田のインタビュー全文はこちら)
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する