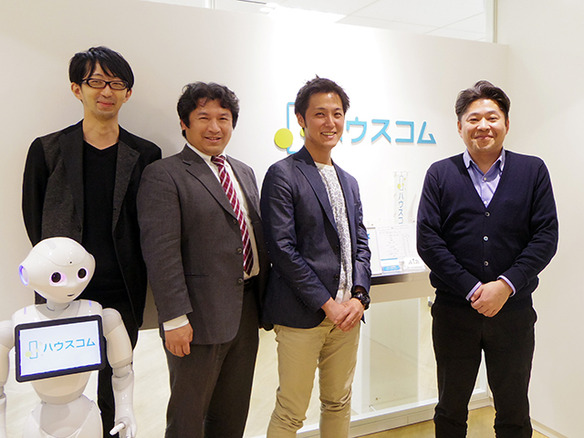
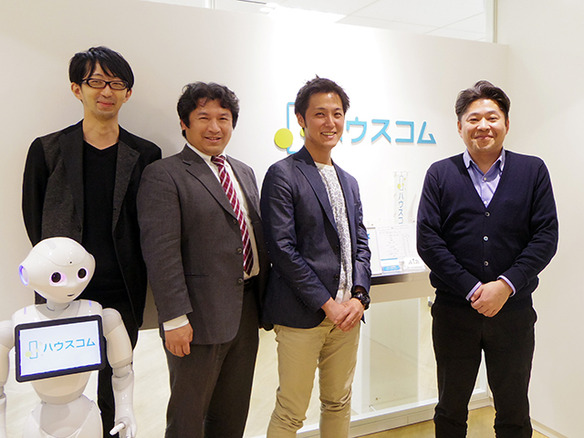
不動産仲介のハウスコムはこのほど、ペットの仮想人格と会話を楽しむことができるスマートフォンアプリ「AI PET(アイペット)」をバージョンアップした。
2017年4月にリリースされたAI PETは、自身が飼っているペットの名前や性格、特長などを簡単な質問に応えて入力していくことで性格づけを行い、アプリに話しかけるとペットのAIが応答してくれることが大きな特徴。ペットの飼育が難しい賃貸物件や単身者にコミュニケーションを楽しめる環境を提供することを通じて、通常は契約時や更新時にしか接点のない不動産仲介と入居者の間に、新たなタッチポイントを形成していくのが狙いだ。
この度の機能拡充では、ペットが行う会話の精度やペットらしさを高めたほか、ペット側から飼い主であるユーザーに生活圏の天気予報を話しかけてくれたり、地域に関連したイベント情報やニュースなどを届けてくれたりするという。そこには、どのような狙いや開発の工夫があるのだろうか。
ハウスコム サービス・イノベーション室の室長である安達文昭氏と、AI PETの開発に関わったレッジのCMOである中村健太氏、そして人工知能の開発を手掛けたデータセクションの取締役CTOである池上俊介氏とビジネス企画統括部/ビジネス企画部/パブリックリレーションズ部の部長である伊與田孝志氏に話を伺った。
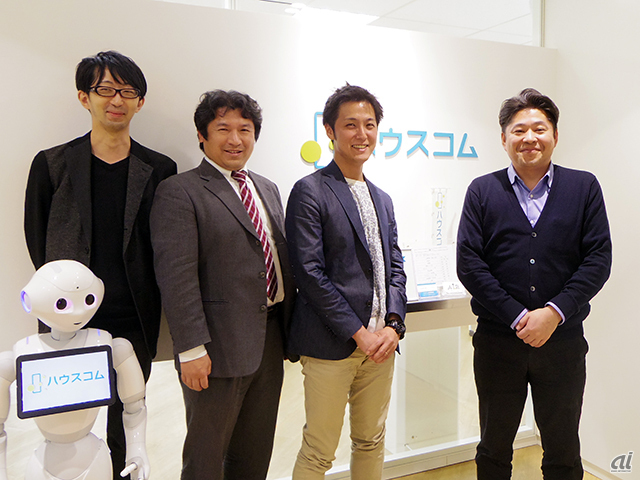

――まずは、今回の機能拡充の背景や狙いについて教えてください。
中村氏:「Google Home」や「Amazon Echo」といったスマートスピーカは、ユーザー側から話しかけない限り機械が話しかけてくるということはありません。アラームも、ユーザーがお願いして初めて機能します。もっと広くみると、ウェブサイトも基本的にはユーザーが目的を持って能動的に探さなければ情報は受け取れません。今回、AI PETが目指すチャットボットは、こうした利用シーンの“逆”を行こうと考えました。

つまり、ペット側がユーザーに思いもよらない気づきを与えてくれるような情報をいわば“勝手に”探して提供してくれるというコンセプトです。当然、ペットを動かすAIに入っている情報は予め人の手で学習させた限られたものですので、提供できる情報に限界はあります。そこで、外部のデータベースと連携させることでAIが学習する情報を増やし、一方でユーザーの居住地域、最寄り駅、職場の地域などからユーザーの“生活圏”を判別し、そこに最適な情報を“ペットがユーザーに届ける”という形で表現することに挑戦しました。
――“ペットが届ける”というところに新しさを生み出そうとしているのですね。
中村氏:スマートスピーカのように、必要な情報を無機質に届けるだけでは、コミュニケーションAIとしてあまりにも無愛想ではないかと考え、“ペットらしく届ける”というところにはこだわりました。今回の開発では、AIが能動的に情報を発信できる仕組みを作り上げる点と、そこから生まれるユーザーの質問やフィードバックにAIがどう応えるかという点を同時並行で進めていき、ユーザーとAIで自然な会話が生まれるようにしました。
常、企業がチャットボットを開発する際には、“こう言われたら、こう返す”というパターンを完全に制御します。しかし、AI PETではあえて考える自由度を高めて、考えながら答えを返すという精度ではかなりの高さを実現できたのではないでしょうか。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する