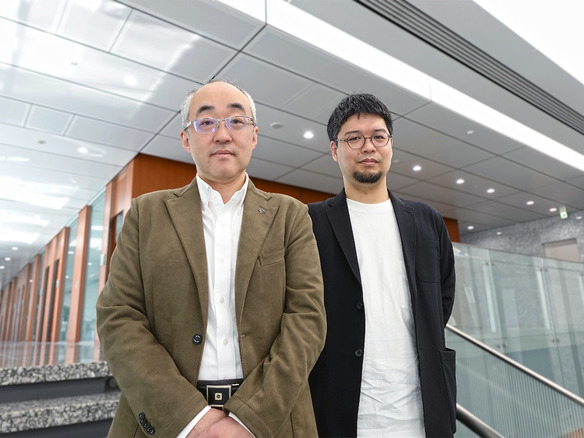
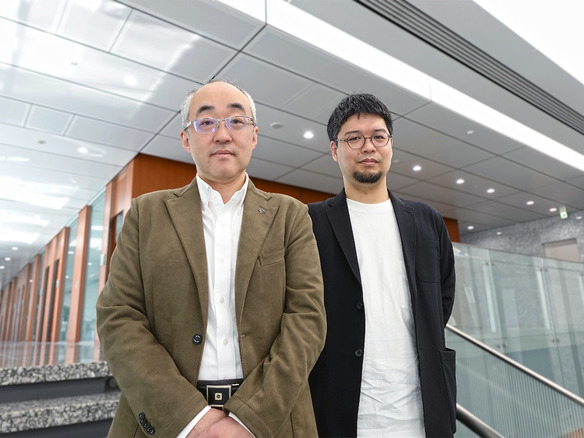
本連載の第1回ではWebtoonの成り立ちと漫画との違いについて、第2回では国内市場の動向について、第3回では今後のWebtoonの未来について、第4回では日本と韓国のWebtoon業界について、第5回では日本のWebtoon業界の現状についてまとめました。
第6回では、集英社の「ジャンプTOON」統括編集長の浅田貴典さん、「ジャンプTOON」編集部・編集長の三輪宏康さんに、この春にローンチされた「ジャンプTOON」についてお伺いします。
中川: 今回は「ジャンプTOON」に絞ってお話を伺います。集英社がタテマンガに参入した理由ときっかけを伺っても良いですか?
浅田: 基本的に、集英社はチャンスを多く与える文化があります。タテマンガ事業も、まず若いスタッフから「こういうのがやりたいんだ」と企画が上がり、浅田がそれをフォローする流れになったことが一番最初の出発点です。
中川: そのとき浅田さん自身は、タテマンガをどう捉えられていたんでしょうか?
浅田: 正直、当時はあまりタテマンガ作品を読んでいなかったというのが実状です。その後いろいろな作品を読み、その結果「あ、おもしろいのある」と思いましたね。「これだったらいけそう」と自分の中でも手応えを感じ、前向きに事業を統括できるなと感じました。
そこから、社内でスタッフのリクルートを始め、面白いコンテンツの目利きが上手そうなスタッフを集めました。当時は、若いスタッフから教えてもらいながら作品を読んでいました。「女優失格」や「外見至上主義」などの作品を寝る間も惜しんで、夢中になって読みましたね。個人的に、弱い人間に寄り添っているタイプの物語がすごく好きなんですよ。そういったストーリー物語は実際にすごく多かったですし、個人的にも好きなジャンルでしたので、今度は「あ、これはいける!」と確信しました。
中川: 自分の好みともハマっているジャンルが、ちゃんと評価もされていたということですね。「ジャンプTOON」の方針や制作にあたって大事にしていることはどういったものでしょうか。
浅田: 「ジャンプTOON」は、ジャンルとしてはわりと満遍なくやっています。なので、男性向け、女性向け、ちょっと汗臭いものや笑えるもの、などいろいろなジャンルを揃えています。その理由は、いろいろ試したいからです。正直、今は経験値が足りないので、まずは自分たちでさまざまな試みをし、経験値を積んでいこうと思っています。その中には、今のタテマンガのトレンドからは外れているものもありますし、タテマンガのトレンドに沿ったタイトルも用意しています。
中川: 編集方針として「続きを読みたくなるか」「繰り返し読みたくなるか」というのがあるとは聞いているのですが、具体的には編集者にはどんなリクエストをして作品を作っているんでしょうか?
浅田: 先にお話しした方針をもとに、スタッフが出してくるものを判断している最中ですね。もちろんこれから先、このジャンルは厚く作れる、このジャンルは弱いなというのが当然出てくると思いますから、その辺りを調整していくと思います。ただ、こういうのをやってくれと、ガチガチに型にハメたくないというのが正直なところです。
三輪: 補足すると、たぶん皆さん「ジャンプTOON」という名前から、どうしても少年誌のジャンプを意識されると思うのですが、我々はあまり「ジャンプ」という名前にひっぱっられすぎないようにと考えています。「ジャンプ」というと男性ものをイメージされると思うのですが、女性ものも含めて試していくつもりです。我々は後発のチャレンジャーですので何でもやらせてもらうつもりです。
我々にできそうなことを探して、そこを強めていくことで「ジャンプTOON」になっていくと考えています。まず、ローンチ時のタイトル、またそこから追加で始まっていく新連載の公開を何度も経て、2年、3年と経つ中で、我々はこういうことをやっていけば良いよね、という軸ができれば良いなと思っています。
中川: なるほど。
浅田: 例えば弊社の「少年ジャンプ+」という先行のマンガアプリがあるのですが、当初(2013年頃)は「カラダ探し」や「終末のハーレム」など、当時のWebマンガの流行りだった、ショッキングなものやエロティックなものが人気を牽引していました。
その後は、「SPY×FAMILY」や「怪獣8号」が出てきたりして、年々“「ジャンプ+」っぽさ” は変わっていきました。変わっていくことは当たり前で、メディアや雑誌を作るというのはそういうことだと思っています。
シンプルにいうと、我々はやっぱり、作家さんとマンガを作る以外のことができないんですよね。とにかく、個人の発想でクリエイティビティを発揮する人たちと一緒になって、作品を作っていく。それが、我々のアイデンティティの底の底の部分だと思っています。
三輪: 一方で、我々はスタジオ制作を否定しているわけではなく、スタジオ制作にはその長所=集合知としての面白さがあると思っています。例えば、数多くの人たちがかかわるスタジオ制作の映画の面白さと、「ジャンプ」のマンガの面白さって、それぞれ異なって、それぞれ良いものという気がしています。
名前が出ている出ていないに関わらず、スタジオの中にも当然人はいて、僕らが知らないところで輝いている作家さんも多くいると思います。そういう方と出会えることが楽しいですし、そういったことも含めて、いろんな作家さんたちと向き合っていきたいです。
中川: おふたりにとって、“縦” のマンガであることはどのような意味があると思いますか?
浅田: 縦型はやはりコマがすごく切りやすく、読み間違いがなく読めるというのは大きいと思います。また、特徴としてはノベルに近いです。ノベルは、クリックするとテキストが表示され、情報が入ってきて、快感が生まれる。Webtoonも同様のケースが多いと思います。主人公に対する没入感がかなりありますし、もしかしたら横に比べると主観性が強いメディアの形式なんじゃないかなと思います。
三輪: 僕らは日本で長年マンガを読んで育っているので、右から左、上から下と自然に読めてしまうのですが、そもそもマンガに触れないまま大人になる人、アニメは観るけどマンガは読まない人、もしくはマンガ文化が存在しない海外の人たちなどからすると、その読み方は理解しづらいかもしれません。
VIZ(VIZ Media LLC)というアメリカの関連会社から出ている単行本には(日本のマンガとアメリカのコミックでは読む順番が逆のため)最終ページあたりに「逆側から読んでね」という趣旨のことが書いてあったりします。その点で言うとタテマンガは絶対に読み間違わない。上から下にスクロールして、セリフも上にあるものから読んでいけば、読み間違えがないのです。これはかなりの強みだと思います。さらにタテマンガは、カラーであることが多いことから、より作中世界をイメージしやすくなります。横読みのマンガと対立する存在では決してないですが、入り口の入りやすさという意味においては、今の横読みマンガよりも優れている部分があると考えています。
浅田: 隙間時間で楽しみやすいという強みもありますよね。
また、制作環境という点でいうと、タテマンガの登場により、物語を書きたい人の総数が増えるのではと思っています。小説家さんや脚本家さんなど、文字で物語を作りたい人が、絵のプロデュースもしたいとなったときに、横読みマンガよりもタテマンガの方が、自分自身で絵コンテを作りやすいのではないかと。
我々はこの春に「ジャンプTOON」のアプリを立ち上げますが、同時に「ジャンプTOON NEXT!」という投稿サイトも立ち上げます。「ジャンプTOON NEXT!」で物語が描きたいという人が投稿してくれるか、集まってくれるか、そして我々が働きかけることができるかが今後の「ジャンプTOON」の鍵なのかなと思っています。
さらに言うと、日本ならではの物語を作りたい人を集められるような仕組みができれば良いなと思います。韓国発祥でタテマンガが出てきましたが、これまでのタテマンガの方向性だけで進んでいるわけではなく、方向性を広げようとしている動きもあります。日本では、いわゆるマンガの文脈からジャパニーズタテマンガらしい作品が出てくるかもしれません。これからはタテマンガ内のジャンルの幅が増えていくのではないかと思います。そのジャンルを発展させるために、多様性というのが必須だと考えています。なおかつ、日本の読者は、世界で有数に物語を欲している人たちであると思うのです。ですのでまずは日本で、ジャンルの豊穣さを創ることができると、そこから世界に飛び出していける。もちろん必要な道程はたくさんありますが、我々の作品は海外も見据えて出していきたいと思っています。そもそも横読みのマンガはすでに沢山の作品が海外展開されていますので。
中川: 海外でよく見ますよね。
浅田: 弊社も「MANGA Plus by SHUEISHA」という「ジャンプ+」で提供している海外向けのサービスがあります。
僕の先輩編集者の言葉でずっと心に残っている言葉があります。「商品とはお金を払ってまでも欲しい作品のこと」という言葉です。我々は商業出版である以上、きちんと商品を作ることにこだわっていかないといけません。きちんと商品を作らないと作家が干上がってしまいます。商品から生まれた利益を作家さんにお戻しできるような健全な仕組みを作ることが我々の仕事ですね。
三輪: 今はXやインスタグラムなどがあるので、必ずしも出版社を通す必要はなく、独自に作品を発表することができます。しかし、その中で我々を選んでいただいて、我々を通じて作品を世に出していくメリットを作らなくてはいけない。僕らは、作家さん一人では届かないお客さんにもきちんと作品が届くようにすることが大事だと思いますし、出版社というフィルターを通すことでクオリティの保証をしていくというか、「ジャンプTOON」のマンガだから面白いよね、という存在になれたら、その時にはじめて作家さんが「ジャンプTOON」で作品を発表する意義が出てくると考えます。作家さんのできないこと、作家さんのやっていることの最大化を常に念頭において仕事をしていきたいと考えています。
中川: なるほど。そうですね、今のお話に関連して、「ジャンプTOON」の短期的、長期的な目標はありますか?
三輪: 浅田がよく言う林業でたとえますと、沢山の木を植えて、その中で育った一部の木がきちんと儲かれば良い、と考えます。全ての木が儲かるわけではないですが、今はまだ小さな木も将来強い大木になるかもしれないので、育てるための投資をしていく。そこは出版社の強みというところではあると思います。我々は植える仕事、肥料をやる仕事、水をやる仕事だけでもしばらく続けていくことができ、いつかの大樹を探すことができます。
浅田: これはいろいろなところで言っていることなのですが、生態系を作りたいと思っています。作家望者がいて、作品を描いて、適切な評価を得ることで実力が育っていき、どこかで大きく花開く。個人的には、本体アプリ「ジャンプTOON」と投稿サイト「ジャンプTOON NEXT!」は、生態系をデザインするための最初の第一歩だと考えています。その生態系を育てるために、長期的な目線で腰を据えて取り組んでいきますよ。
三輪: 読者は、タテマンガだから読む、横読みマンガだから読む、といったこだわりがあるわけではないのはないでしょうか。手に取って「面白い」と思ったら読んでくれる。最初は、とりあえず手に取ってもらえるまでのハードルをどんどん下げて、ふとマンガを読みたいときに開いたアプリが「ジャンプTOON」だったら嬉しいなと思っています。
浅田: 「ジャンプ」らしさをあえて語るのであれば、そのときどきの時代で若い編集と若い作家が試行錯誤して作り上げてヒットしたものが、それが既に「ジャンプ」なんですよ。「MANGA Plus by SHUEISHA」でも「カグラバチ」というタイトルがきっかけになって、サービスがますます流行り出したと聞いています。それもまた、編集と作家と読者との共生関係と言いますか、それぞれ編集も作者も読者も変わっていくので、その時代に合わせて変化をしていくこと自体が「ジャンプ」なのではないかなと思います。
中川: すごい良い締まり方だったなと思います。ありがとうございました。
中川元太
株式会社Minto 取締役
2010年に大手インターネット広告代理店に新卒入社。札幌営業所長を経て、2013年より漫画アプリ「GANMA!」の運営会社の創業メンバーとして漫画編集チームとアプリマーケチーム等を立ち上げる。2016年にSNSクリエイターのマネジメント会社・株式会社wwwaapを創業。2022年に株式会社クオンと経営統合し、株式会社Mintoの取締役に就任。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する