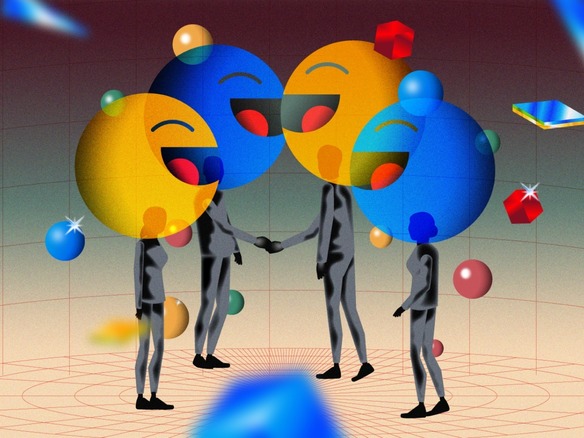
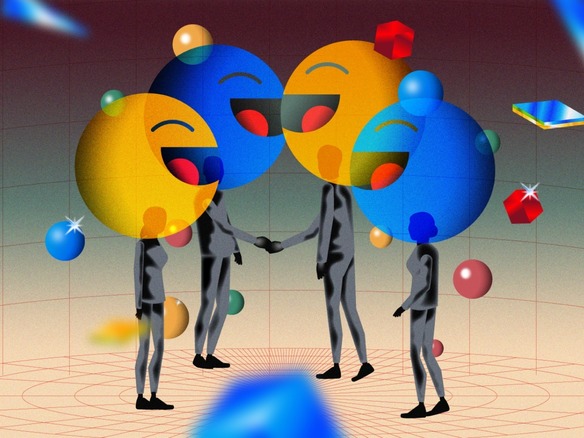
Wirth氏は、観客参加型の演技と即興に関するベテランであり、アバターを通じてアイデンティティーを表現するワークショップになる空間をVRで構築し始めている。筆者は、没入型シアターの環境を何年も追ってきた中でWirth氏に出会ったので、同氏のプロジェクトのことを耳にしてすぐ、その体験への参加を申し出た。
Wirth氏は、VRにおけるアバターの大げさな演技を、われわれが実生活の中で演技を習得するプロセスに近いと考えている。VRツールに慣れるにつれ、どんどん自然になる。
コロナ禍が始まって以来、誰よりも近い距離で演者たちの隣に立っていると、会話はより自然に感じられるようになった。この体験は、マンガのようなアバターを介していてもリアルだったのを覚えている。顔の表情が足りないのを補うように、話すときには、両手をもっと使おうと試みた。
Wirth氏が説明するように、われわれはボディランゲージと表情が仮想空間でコミュニケーションの役割を果たすという前提に立っており、そうならない場合に、コミュニケーション不全と疎外が生じうる。そこが、議論の始まりにも、あるいは断絶の始まりもなる。
これは理解できるし、常に感じていることでもある。そして、仮想世界でどうコミュニティーを築いていくのか、その始まりとも思える。

Wirth氏は、オンライン上の衝突のほとんどが断絶状態に起因すると考えている。ひと昔前のネットにおけるののしり合いもそうだし、今でいえば不完全ながら感情を代弁する絵文字もそうだ。テクノロジー大手各社がメタバースにおける人間同士のやり取りに関する部分を最後まで後回しにしているのも偶然ではない。解決が最も難しい領域だからだ。
「プログラム的に、実現するのが最も難しいのは、われわれを特に人間らしくしている各種の要素だ」。そう語るWirth氏が感じているのは、VRにはまだ十分に発達したボディランゲージが確立されていないということだ。同氏は、練習と意識的な努力でそれは実現できると考えている。今はまだ、奇妙な補助器具頼みだ。手にゲームコントローラーを握り、頭に大きいヘッドセットも装着しなければならない。アイトラッキングとハンドトラッキングによって、今より自然で微妙なボディランゲージも実現しそうだが、カメラやセンサーがたくさん付いたヘッドセットに追跡されて、気持ちよく信頼できるものだろうか。
筆者自身はいつの間にか、信頼して耳を傾けるように、そして自分の動きを意識するようになった。ある練習では、コントローラーの動きを小さくして、普通に歩くのと同じスピードで仮想的に歩くことを学んだ。実験的な練習ではあるが、実際に仮想世界の中にいるということを、より強く意識するようになる。筆者はいつも、テレビゲームを遊んでいるときのように跳ね回ろうとする癖がある。だが、実際にそこにいるということをもっと意識すれば、その環境をより尊重した行動をとるようになる。
たとえ、最終ゴールははるか彼方だとしても、それは、つながりやコミュニティーを模した世界に向かう、小さな1歩だ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する