なんとなく、アナログ的な古い慣例が残っているイメージの強い不動産業界。近年はあらゆる業界でデジタル化、DX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた動きが活発になってきているが、レガシーの筆頭のように見られていた不動産業界にもDXの潮流が生まれ始めている。特にこのコロナ禍で顧客とのコミュニケーション手段に変化が訪れたことが、1つのターニングポイントになったようだ。
ところが、そのことがかえって積極的にDXを推進する事業者と、そうでない事業者の2極化を進める結果にもなっているという。本誌CNET Japanが主催した「不動産テック オンラインカンファレンス2020」では、「不動産のDX、進む会社、進まない会社」と題してパネルディスカッションを実施。とりわけ一般の多くの人がなじみのある住宅の売買、賃貸に関係する不動産業において、DXはどんな状況にあるのか、そして古い体質の不動産会社がどうすればDXを進められるのか、不動産関連サービスを提供する立場にある3名のパネリストが意見をかわした。

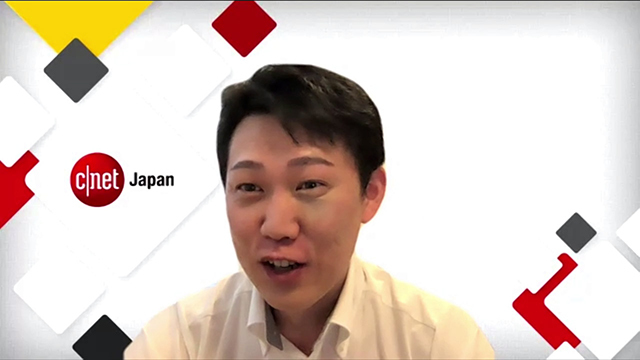

パネリストの1人は、不動産営業担当者向けの顧客コミュニケーションツール「アトリク」を提供しているサービシンク 代表取締役の名村晋治氏。同氏によると、同社と取引のある不動産会社においては、外出自粛が求められて店舗を閉めざるを得なかった3~4月にかけて最も売上への影響が大きく、物件の内見や契約が全部ストップしたところもあったとのこと。契約の可能性がある顧客に対して行う、不動産業界では一般的な「追客(ついきゃく)」と呼ばれる営業活動すらままらないことが、一番の懸案事項になっていたという。
ただ、そんななかでも同社のアトリクを導入しているところや、そのほかのチャットツールでコミュニケーションを図っていた不動産会社は「薄いながらもお客様とつながっていた」。それらチャットツールが、対面や電話・FAXを使う従来のやり方に代わる新しいコミュニケーション手段になりつつある、との印象をもつ不動産会社がコロナ禍で増えてきたことも名村氏は実感している。

顧客とのコミュニケーション改善を主眼にした同社のアトリクは、前置きなしで簡潔に連絡可能なチャットツールとして利用できるのが特徴。不動産営業スタッフの多くはこれまで、顧客とやりとりするために電話を何度もかけ直したり、長文メールの作成に必要以上に手間をかけたりしており、決して効率的とは言えない、「追客にかける時間を減らす」ことが同ツールの目的だ。
「いずれ人口減少でお客様の取り合いになると、不動産仲介会社においても顧客満足度が求められてくる。付加価値を高めるにはお客様1人1人への提案(の検討)に時間をかけるべきで、そのための作業の時間を増やすべきではない」というのをモットーとしている。
アトリクを導入したことで、不動産会社では顧客とのコミュニケーションにかける時間が3分の1になり、成約率が向上したという明確な成果も上がっている。コミュニケーションを短縮できたことで多数の顧客を同時並行でフォローしやすくなり、業務効率が上がっただけでなく、「営業担当の負荷が減って、働き方改革にもつながっている」と語る。
顧客とのコミュニケーションにLINEなどの個人向けツールを活用している不動産会社もある。しかし、その場合はとりわけ女性の顧客にプライベートに踏み込まれるような忌避感を持たれるのが1つの壁になっている。システムの仕組み上、顧客とのやりとりを不動産会社内のほかのスタッフも目を通すことになるアトリクであれば、そういった面からも安心してメッセージ交換ができると納得してもらえるメリットもあるようだ。
ただ、歴史の長い業界だけに「変化を怖がっている会社」もまだ少なくない。そうした新しいツールを避ける会社は、DXを進められないところの最たる例だとするが、いずれにしろ同氏はもはや「DXからは逃げ切れない」と見ている。DXをすでに進めている不動産会社はもちろん、エンドユーザーも「便利なツールがあることを知ってしまった」ため、今後それがない環境をわざわざ選ぶ可能性は極めて低い。DXを進めずにいる不動産会社は時代に取り残され、DXに取り組む企業との差は今後ますます広がるだろう。
DXを進められる会社になるかどうかは、「変化していかないと、という危機感を持てるかどうか」が重要だと同氏。「やるかやらないかではなく、いつやるか。2021年1月の繁忙期が大きな分かれ目になる」と予測したうえで、それまでの残りの3カ月間に1つでも新しいことに挑戦し、1日に対応できるお客様を1人増やす、といった小さなところからでもスタートすることの大切さを訴えた。

2人目のパネリストは、スペースリー代表取締役の森田博和氏。物件の内見を360度映像のVRで仮想的に行えるシステムを開発しており、不動産売買だけでなく、企業の研修や営業ツールとしても活用されている。4月のVRコンテンツの利用度合いは2019年同期比の3.3倍にまで拡大しており、「消費者が(VRコンテンツのような新しい情報を)求めているという変化が感じられる」と同氏。それに合わせて不動産会社においても情報発信の重要性が再認識されるようになってきている、と分析した。
森田氏によると、ある不動産会社では3月、全体の85%が内見なしに契約に至ったとのことで、VRコンテンツによって物件探しのスタイルは大きく変わってきている。しかしながら名村氏も語っていたように、消費者が「便利なツールがあることを知ってしまった」ことは、長期的には不動産業界にとってポジティブにもネガティブにもなり得る、と感じている。テクノロジーを使いこなしている不動産会社と、そうではない不動産会社に2極化が進み、必然的に生き残る会社が絞られる結果になると考えられるからだ。
どうすれば生き残る不動産会社になれるのか。森田氏は不動産業界にもそのほかの業界にも通用する「DX推進に必要な三大条件を見つけている」とし、その内容を披露した。1つは意志決定するマネジメント層の人間が強く決断できるかどうか。電話、FAX、メールのようなアナログに近い手法から、チャットツールを活用したコミュニケーションに変える、ということにすら不安を感じて決断できない不動産会社も現実には多い。しかし、「効果がなければ簡単にやめられるのがITツールのいいところ」でもあると同氏。少なくともチャレンジして「悪くなることはない」ため、まずは始めることが重要だとした。

2つ目は、会社が決断したときに、それを現場で推進する人物を立てることができるかどうか。最初に1店舗でトライアルを始め、成功すればそれを他店舗にも広げていく、という流れを作る推進者が必要ということだ。そして3つ目の要素として、不動産会社自体ではなく、「我々のようなDXに向けたITツール・サービスを提供するサプライヤー側が不動産会社を徹底的にサポートできるかどうか」も鍵になってくると語る。
ツールをただ渡して終わりにするのではなく、不動産会社が最も高く問題意識をもっているところに対して、的確なツール選定と効果的な活用方法を提案し、手厚いサポートを行うことでDXの成功に結び付くこともあると訴える。「現場でシステムを使いこなせずに断念するパターンもあるが、当初とは違う目的で使えばうまくいくこともある。そこはサプライヤーのやり方次第」というわけだ。
不動産会社によって課題感は異なるが、現在、多くの会社が問題意識として抱えているのが「歩留まりを上げる(成約率を上げる)」ための方法論だという。同社のVRコンテンツはそれに対して高い効果も得られると森田氏は話すが、「DXは“若い人の意識が変わる”というのが大事なこと」だと付け加える。不動産会社がDXのような新しい取り組みに積極的になることで、特に若手社員のモチベーションアップや離職率の減少につながる効果もあるとし、それを理由にDXをアピールしている企業も増えているという。
ただ、あくまでもDXは「消費者に求められて変わっていくもの」であると森田氏は釘を刺す。DXは企業の成長を促すものでもあるが、コロナ禍であらゆる面からオンライン化が進んだことにより、マーケットや消費者のトレンドは大きく変化し始めている。今後もその変化の度合いによってはDXに求められるもの、実現すべき目標も変わっていくに違いない。同氏は最後に、「オンライン化で得られたデータをいかにして活用していくか」がDXを正しく導くうえで課題になってくるだろうとした。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する