

日清食品ホールディングスと東京大学 生産技術研究所 は2019年3月、サイコロステーキ状の牛筋組織を作製することに世界で初めて成功したことを発表した。同社は肉本来の食感を持つ「培養ステーキ肉」実用化への第一歩だと語る。その取り組みの背景や“食”の新しい世界を生み出す可能性について、日清食品グループ グローバルイノベーション研究センター 新規事業推進室 兼 健康科学研究部 課長 仲村太志氏と、日清食品グループ グローバルイノベーション研究センター 健康科学研究部 古橋麻衣氏、東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授 兼 生産技術研究所 教授 竹内昌治氏に聞いた。
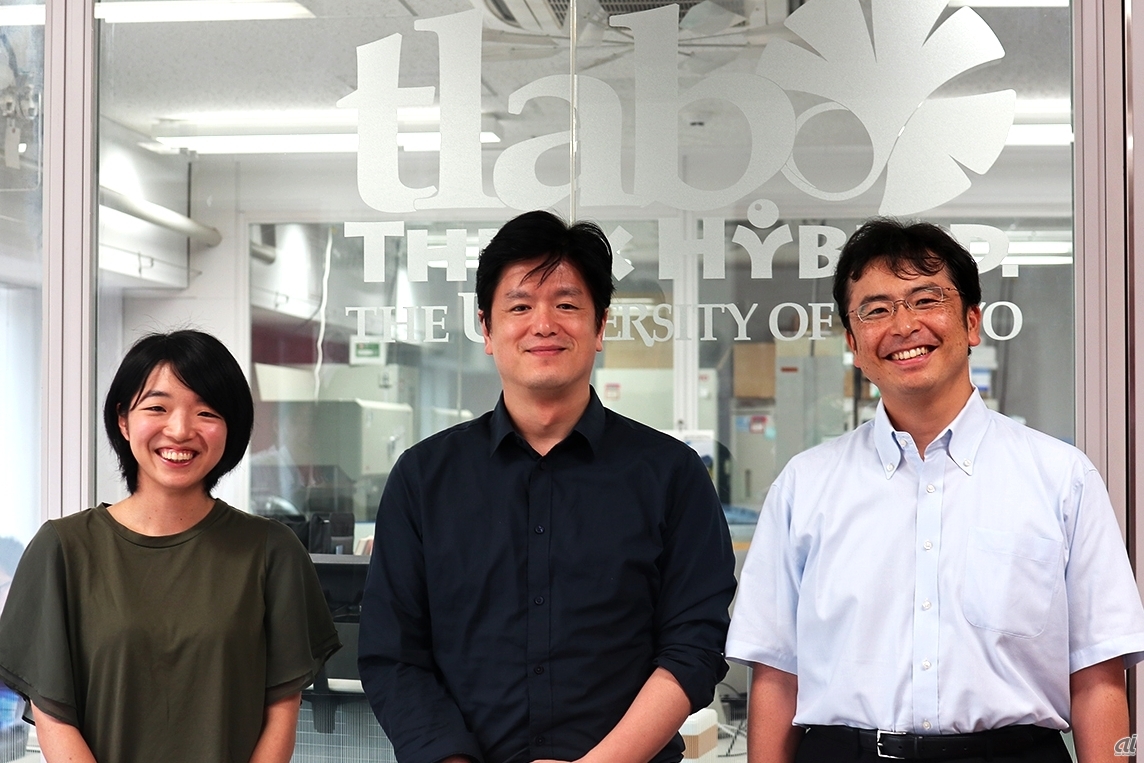
――2019年3月22日に牛筋組織の作製成功を発表しましたが、本プロジェクトはどのように始まりましたか。
竹内氏:東大側としては10年ほど前から、体外で細胞から3次元の組織を作る再生医療や組織工学の研究を続けています。その1つのアプローチとして医療や創薬への適用と“お肉作り”がビジョンにありました。ただ、研究費は欠かせません。そのため、医療寄りで研究は続いていましたが、将来的な展望を踏まえて“筋肉作り”にも取り組んできました。10年ほど前から財団や政府、企業など各方面に「肉やりませんか」と、お声がけを続けてきましたが、願いかなわずといったところに、日清食品から「ぜひ」との声をいただいて2017年8月より共同研究がスタートした次第です。
昨年2018年にJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)が実施している未来社会創造事業の1つとして“動物性タンパク質の未来を考える”プロジェクトがありました。そこにいわゆる培養ステーキ肉プロジェクトとして「3次元組織工学による次世代食肉生産技術の創出」というプロジェクト名で共同応募して採択され、2018年10月から探索研究としてプロジェクトが始まった次第です。その成果を発表したのが3月ですね。
成果として「お肉を食べられる」のかといえば、僕らも食べていません。製品として販売する段階にも至っていません。ただ、培養肉が社会に受け入れられないと、食べてもらえる機会も得られないでしょう。ですから僕らのスタンスとして、初期段階から情報を公開して、見守ってもらいながら研究を続ける姿勢でおります。

――それでは、日清食品側のプロジェクト開始に至る流れも教えてください。
仲村氏:日清食品としては食糧問題が確実に発生するという課題に取り組もうという思いがありました。チキンラーメンやカップヌードルからもお分かりいただけるとおり、弊社は世の中のために新しい食を作り出すことに注力しています。この観点から培養ステーキ肉を通じて、食糧問題を解決できないかと考えていた際に竹内先生の存在を知り、共同研究に至りました。それが2017年夏ごろですね。
(社内の稟議プロセスが課題となるとの質問に)最初は皆が大手を振って大賛成というわけではありませんでした。ただ、弊社は新しいことに取り組むことに寛容なので、「取りあえずやってみよう」と。ただ、最近は学会発表やメディアで紹介されるようになり、社内評価も格段に改善しました(笑)。
本プロジェクトに関して、まずは技術の確立です。もちろん時間はかかりますが、何らかの形で世に送り出し、お客様に届けることを考えています。

――先ほど「探索研究」というキーワードがありましたが、これは何でしょうか。
竹内氏:PoC(概念実証)ですね。我々が目指すことが本当に実現できるのかを確認する段階で、これを経て本格研究に至ります。最近はこのようなプロジェクトが少なくありません。
――改めてお聞きしますが、竹内先生はなぜ肉に注目されたのでしょうか。
竹内氏:体外で細胞を増やして、組織や臓器といった3次元構造を作製することで、できたモノを体内に埋め込めば再生医療につながります。たとえば犬の鼻を作れば、人間の1億倍ともいわれる嗅覚センサーを作ることができるでしょう。さらに人間の皮膚組織を作れば、化粧品が皮膚に及ぼす生体反応を知ることも可能です。このように多様な利用法が存在する中で、他の可能性を考えたところ、牛の肉の組織を作れば食べられるよねと。もちろん私独自のアイデアではありません。20年前ごろから世界で語られてきたものですが、我々の技術がそのような研究にも関与できることから興味を持ちました。培養肉は動物から細胞を搾取し、体外で培養してお肉として形成したものです。
――話は変わりますが、古橋さんは(東京大学の研究所に)常駐されているんですか。
古橋氏:はい、ほぼ常駐しています。培養ステーキ肉というテーマが開始する段階から参加しました。世界的に食肉需要が増すなかで畜産牛の増加が見込めないケースや、海外でも環境破壊や動物愛護の視点で培養肉の利点は多く語られています。日清食品として現状課題に対して、包括的に解決できる手段として培養肉の存在は大きいと認識しています。ただ、まだまだ研究途上であり、国内外ともに実用化前段階でしたので、本格的に取り組んだ次第です。ただ、応募ではなく企業から任命されました(笑)。

仲村氏:ちょうどタイミングが重なったんですね。
古橋氏:それまでは新人研修でした。ただ、大学との共同研究を新入社員に担当させる企業は多くありません。弊社の場合、他の研究テーマでも新入社員が任命されるケースもありました。
――そうしますと、2年以上プロジェクトに参画していますね。
古橋氏:そうですね。8月で丸2年です。
竹内氏:新人とは思えない活躍ですね。日清食品の育て方が素晴らしいのか、古橋さん個人の能力なのか分かりませんが、彼女がいないと研究が進みません。
――それでは具体的な研究内容をお聞かせください。
古橋氏:牛の筋細胞を体外で組織化する研究を続けてきました。竹内研では、筋肉細胞から組織を作って再生医療やロボットに活用しようという研究も行われいます。これらを牛の筋細胞に適用させました。ただ、食べるとなると一定のサイズが必要になりますので、いかに技術を応用してスケールアップし、牛の細胞に適用させるか研究を重ねています。
――つかぬことをお伺いしますが、“培養肉”という呼称でよろしいですか。
竹内氏:たとえば英語なら「Cultured Meat(カルチャードミート)」「In vitro meat(インヴィトロミート)」などと呼ばれますが、日本語版として「培養肉」で進めてきました。おいおい適切な表現が登場すると思っていましたが、2019年3月以降はマスメディアがこの呼称を使うようになり、社会での認知度も高まりました。個人的にはこのままで良いと思っています。もちろん、商品化といった場合は別ですし、名称に関する議論はありますが、テクニカルタームにおいては培養肉が浸透してきています。
――素人目線では遺伝子組み換え食品と混合する見方があります。このあたりの説明もお願いします。
竹内氏:遺伝子組み換えは一切考えていません。たとえば米国で許認可されても、日本では大きな抵抗を覚える人がまだ多い状況かと思います。細胞をそのまま培養するわけですから、遺伝子組み換えは必要ありません。自然な形でお肉として形成し、提供することを目指しています。
仲村氏:出来上がるものに遺伝子組み換えを加えますと、自然世界に存在しないものになりますよね。我々は自然にある本物のお肉と同じものを培養という手段で作り出せる世界を目指しています。
――加えて素人目線ではクローンというキーワードも登場します。こちらも関係ないのでしょうか。
竹内氏:クローン技術はやはり遺伝子を操作するものですよね。僕らの取り組みとは異なります。
仲村氏:クローンというアプローチでは、牛を育てなければなりません。通常の畜産と同じく餌や牧場の用意が必要です。
――現段階では難しい質問だと思いますが、実用化は何年先になりそうですか。
竹内氏:今の世界最先端技術を持ってしても、細胞を体外で培養して我々の筋肉と同等のものを作り出す技術は存在しません。現状を説明しますと、細胞が融合し筋組織となり、それが集まったのが筋肉です。さらに生体筋肉に近づけるには一方向に整えることも重要です。
我々が成功したのは、初期段階である筋肉を融合して組織が揃ってきた段階であり、その先にあるさらに成熟した形態や機能の再現には至っていません。一方で、完全な筋肉の完成を待たなければ、お肉として食べられる段階にならないというわけではなく、それ以前の段階でも食べられる形態はあり得ると考えています。我々は、生体の筋肉に近づけば近づくほどおいしくなると信じていますので、より完成度の高い肉づくりに常に取り組みつつ、各段階で食肉として世の中に出していけるような体制をとっていきたいと考えています。
仲村氏:基本的な技術の確立は2025年を目標にしています。
竹内氏:(可能性を問われた上で)僕は頑張ろうと思っています。培養肉研究が大好きですから。早く食べられるようにしようと思っています。欧米では培養肉のスタートアップが多数登場しており、来年2020年には培養肉バーガーが市場に登場するともいわれています。
仲村氏:我々の研究と大きく異なりますが、彼らはミンチ肉なんですね。我々はステーキ肉を目指しています。
竹内氏:ミンチ肉は組織が小さく、培養も比較的容易です。一方で、厚みのあるステーキ肉のように一体化するには細胞をきれいに並べて融合させることが重要ですが、厚さ方向に細胞を積むと中まで養分を供給しないと細胞が死んじゃうんですよ。細胞を生かしたモノづくりという意味では苦労が多いですね。
課題としては食感や味という観点もあれば、牛筋組織を通したけれども脂肪や血管の挿入方法など技術的な課題もあります。さらに社会受容に対する課題もあり、モノづくりを理解していただき、「食べたい」と思ってもらえるような社会受容。さらに法的な規制ですね。新たな食品を生み出すわけですから、役所の理解を得られるかなど議論しなければなりません。
――この話を踏まえて日清食品側の課題はありますか。
仲村氏:技術的な取り組みはいずれクリアできますが、やはりお客様の受容性を高められるかでしょうか。弊社の調査によれば、まだ受容性は高くありません。認知度向上と受容性アップ、そして食品企業としては安全安心に食を届ける使命があります。それらを証明しつつ、世に提供するステップが重要だと考えています。
――竹内先生の長期的ビジョンをお伺いします。社会課題を踏まえますと肉に限った話ではありません。今後、研究成果を社会課題に活かしますか。
竹内氏:もともと機械工学が専門なんです。工学者はPCやロボット、自動車など便利なモノを作ってきましたが、それらのモノづくりに使用する材料は金属やプラスチックといった人工物に限定されています。従って、たとえば自己増殖や自己修復といった生物が持つ魅力的な機能は簡単には組み込めません。であれば、生物を構成する細胞をモノづくりの材料として使う、"細胞を使ったモノづくり"を行なうというのが、我々の研究のスタンスです。その1つの出口が培養肉です。
仲村氏:あくまでも培養ステーキ肉は1つのアウトプットでした、牛肉に限らずマグロやウナギでも構いません。枯渇する資源に活用できればと、適用範囲を広げたいと考えています。
竹内氏:培養ステーキ肉への取り組みは、現在の再生医療が抱えている課題と同様です。日本は再生医療に研究・投資してきましたが、その技術が培養ステーキ肉研究にも転用され、ゆくゆくは互いを高める技術に発展することは十分にありえるでしょう。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する