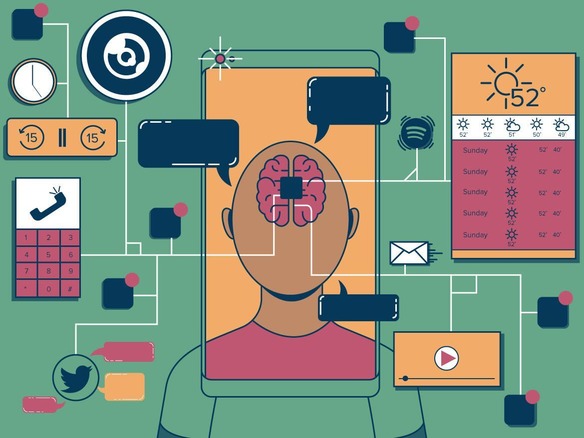
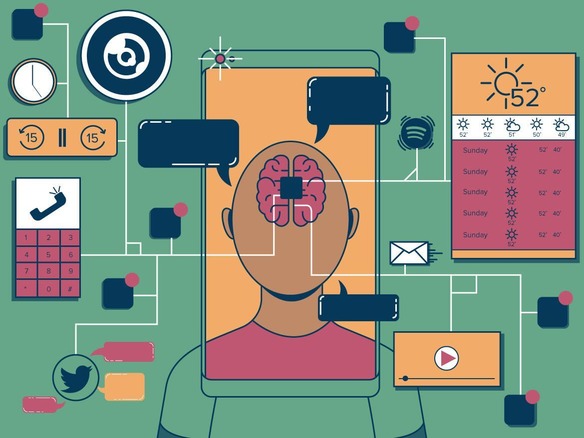
筆者の手には、チップが埋め込まれている。これは本当の話だ。
2年前、ベルリンで開かれたテクノロジ見本市の楽屋裏で、入れ墨をした男性が注射器でチップを注入してくれたのだ。耳にピアスの穴を空けるときくらいの痛みしかなく、所要時間も同じくらいだった。チップは米粒ほどの大きさで、それまでとは違うスマートフォンの使い方ができるようになった。だが、正直に言うと、筆者がこの処置を受けてみたのは、純粋にジャーナリストとしての動機からだった(記事のためなら、大概どんなことでもする)。
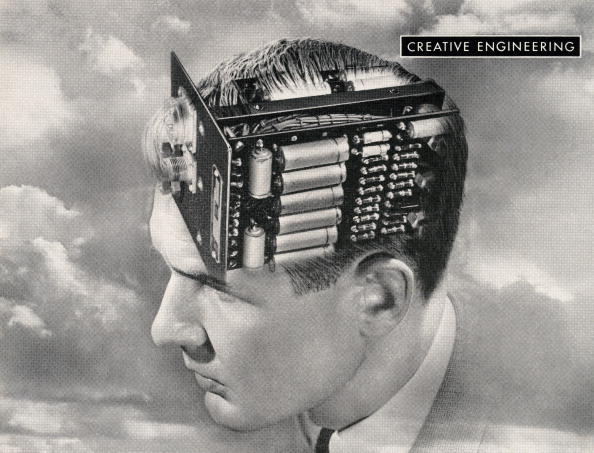
「アップグレード」という点では、筆者の体験はおおむね無害で、大ごとでもなかった。だが今や、人間の脳を増強して「超知性」を発達させようと考えている企業家もいる。そうなると、脳にテクノロジを埋め込む、いわゆる「ブレインコンピュータインターフェース」を作る処置が必要になるだろう。
これは、人工知能(AI)とロボット工学の発展に対する過剰な反応のひとつと見なすこともできる。この発展については、人類にとって最高の出来事と考える人と、最悪の出来事と考える人に二分される。Stephen Hawking氏やElon Musk氏といったテクノロジの権威は、このテクノロジの誤った使われ方について悲観的な立場で警告を発している。だが逆に、テクノロジを利用して人間の能力を強化するチャンスであり、AIとの連携さえ可能だと考える立場もある。Musk氏自身が立ち上げた企業のひとつは、そちら側だ。
自身の会社Kernelで、脳を増強する機器を開発しているBryan Johnson氏は、11月にポルトガルのリスボンで開催された「Web Summit」で、次のように語った。「私が最も懸念しているのは、人間には協力できるだけの能力がないことだ。協力することができれば、われわれは問題を解決できる。問題解決という目標に向かって、われわれが一丸となって取り組むことを私は願っている」
ブレインコンピュータインターフェースができれば、人間同士のコミュニケーション(そう、テレパシーのような話だ)だけではなく、人とコンピュータとのコミュニケーションも実現するかもしれない。理論上は、AIと連携して、世界中の難問を解決することだって可能になる。
そういった意味で、Johnson氏が試みようとしているのは、人類にとって一種の危機管理対策だという解釈も成り立つ。
「未来に向けて、人類が適応するために必要なことだと考える」とJohnson氏は述べている。そうしなければ、人類は適応能力の点でコンピュータに劣ることになり、取り残されてしまいかねない、というのである。

誰もが超知性を恐るべき存在と考えたり、そもそも実現性のある見通しとして捉えたりしているわけではない。英国のシェフィールド大学で人工知能、ロボット工学、パブリックエンゲージメントの名誉教授を務めるNoel Sharkey氏によれば、人間と同等の知性を持つマシンなど、まだ遠くはるかな夢にすぎず、今は基礎的なことを正しく行うことに専念すべきだという。
12月に実施したインタビューで、Sharkey氏はこう答えている。「私に言わせれば、超知性に目を向けるというのは、高速道路を走っているときに遠くを見すぎて前方の車に衝突してしまうようなものだ」
しかし、こうした考え方も、人を支援するという試みを妨げてはいない。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する