続いて登壇した粂氏は、EHR(Electronic Health Record:複数の医療機関で発生した個人の医療記録を生涯にわたって保存・参照するための仕組み)の研究を専門とする。粂氏によれば、人々の生活のなかで蓄積される情報を分類していくと“健康”に関するデータ容量は極めて小さいという。
医療機関に蓄積される医療データを介護や看護といった視点で活用しようとするとき、個人の食生活や普段の活動といったデータが欠落し、医療との相関図が見えない。「さらなる健康データの蓄積がHealth 2.0に求められる」(粂氏)

粂氏の説明で興味深いのが「ウェブと医療」というテーマだ。「2002年以前のWeb1.0時代は、信頼性のある医療情報の一方的な提供に留まっていたが、その後のWeb2.0では医療関係者や患者同士のSNSなどが登場し、これらはユーザー数を拡大していった。一方、Health 2.0は、データを共有するという概念は同じながらも対象が限られていたため、ビジネスの成功やユーザー数増加は実現しなかった」と分析する。
その結果、ユーザーが自分の健康状態を連続的に取得する「PHR(Personal Health Record)」が生まれたものの、当初は手動入力が必要なため浸透しなかったという。粂氏はIT企業の大手であるGoogleの「Google Health(2008~2012年)」を引用し、「Googleでも難しかった」と見解を述べた。
PHRは個人が主体となるのに対して、EHRは医療機関がデータを蓄積する仕組みだ。「政府が予算を割り当てたことにより、国内では20年前から取り組みが始まっている。その点において日本は先進的だ」と説明しつつも、患者の一生涯にわたる医療情報を永続的に保存する概念は実現できなかったという。
最終的にEMR(Electronic Medical Record:電子医療記録)やEHRとPHRとつなげて、重複検査の削減や横断的な研究を実現する世界を目指していると、自身の活動を説明した。
次に登壇した日本IBMの久世氏は、IBMが開発した自然言語を学習して人間の意思決定を支援する「Watson」がIT医療に与える影響について、事例を中心にプレゼンテーションを行った。
2011年2月にWatsonが米国のクイズ番組で優勝すると、多くの企業からWatsonを使えないかという連絡があり、その中で特に多かったのが医療分野の企業だったという。久世氏は「医療の世界では新しい症例や治療方法が増えているものの、米国の医療従事者は月間5時間しか学習時間を確保できない」と現場状況を紹介しつつ、「Watsonで医療従事者をサポートする」と役割を説明した。
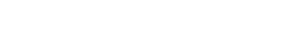
IBMは、がんの症例160万件とがん専門誌40誌200万ページをWatsonに学習させて、患者の症状や家族の病歴からがんの可能性を予見する「Watson based adviser」を2011年から約4年間かけて開発した。
その他にも、ゲノム医療の文献やパテントを分析して遺伝子異常や症状を分析する「MD Anderson Cancer Center」や、医療保険承認審査システムの「WELLPOINT」でもWatsonは活躍している。最終的にIBMは膨大な健康と医療情報を収集し、分析や予測結果の上で個々に合わせたヘルスケアを提供する「IBM Watson Health Cloud」を目指すとしている。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 無限に広がる可能性
無限に広がる可能性
すべての業務を革新する
NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する