
新たな発想で開発された情報分析プラットフォーム「QlikView」を展開する、クリックテック・ジャパンは3月6日、東京・港区内で「Business Discovery World Tour in Tokyo」を開催、「QlikView」の概念、その威力、事例などを広く紹介した。基調講演1では、米クリックテック プロダクトマーケティングバイスプレジデントのジェフ・ビーム氏が「ビッグデータから意味を見出すべきはビジネスの現場」との表題で、「QlikView」の理念、概要などについて解説した。基調講演2では、グーグル クラウドプラットフォームセールススペシャリストの塩入賢治氏が「Googleスケールで実現するビッグデータの世界」と題し、ビッグデータの効用について説明した。

米クリックテックのビーム氏は、Google、Apple、Salesforceなどの例を挙げ「これらの各社は、検索、モバイル、SaaSの分野で、大きなイノベーションを成し遂げた。 そしていずれも共通するのが、使う人にとって簡単であるということ。クリックテックも同様に、BIをだれもが使いやすくなる技術により、革新をもたらした」と述べた。
同社の「QlikView」は、「Business Discovery プラットフォーム」と呼ばれる、新たな発想で開発されたユーザー主導型のBIだ。開発当初からインメモリの可能性を見越し、基本技術として採用した。これにより、ユーザーが画面操作をした瞬間に、その場で高速計算し、データの関連性を高い視認性でもって表示できるようになった。それだけではなく、データを元のサイズの10%に圧縮するため、大量データにも対応が可能となった。それを支えるのが、「連想技術」という特徴的なテクノロジーだ。
従来のBIは階層構造であり、これを順にたどってドリルダウンしていく手法だ。そのため、どのような軸でデータを見たいかという階層構造が先に定義される必要があった。導入後、まずは地域別で見たいのか、製品別に見たいのか、担当者別に見たいのかといった項目を定義する作業がある。そしてデータソースを確認、DWHを開発し、データマートを開発し、ユーザーインターフェースをつくる--との流れになる。
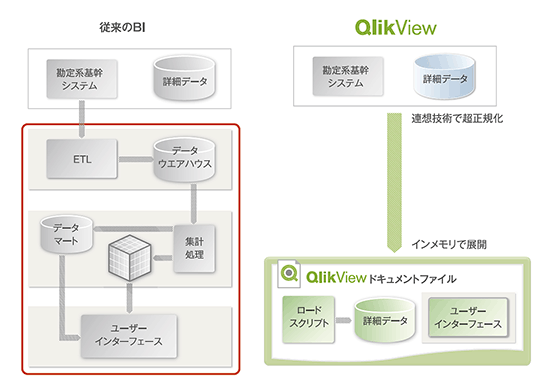
いっぽう「連想技術」では全てのデータの関連性がメモリ上で自動的に保持されているため、階層を定義する必要がない。さまざまなデータソースからデータを取り込み、次いでユーザーインターフェースを開発するという工程だ。つまり「どのようにデータを見るか」というのは、そこから決めていくことができ、これまでのBIと比べると工程が逆転している。また連想技術では、同じ項目名で、同じ値の情報は物理的に一度しか保持しないのでデータ構造がすっきりし、サイズも大幅に削減される。
取り込まれたデータをたどる際は、"連想"を軸に、地域からであろうと、担当者からであろうと自在だ。担当者をみて、どの製品が売れているか、あるいはどの地域で売れているかなど、どの項目からでも分析を開始することができ、分析軸を自由に切り替えることで、どんな切り口でもデータを分析することができる。
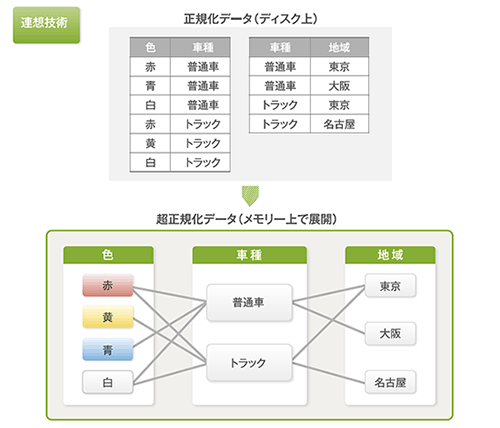
ビーム氏は、「四半期ごとの利幅はどのくらいなのか。ある地域では目標が達成できていないのはなぜか。この地域では自転車が売れていない理由は何か。ビジネス現場のユーザーはさまざまな疑問を持つ。「QlikView」の場合、ユーザーが思いついた質問を投げかけて答えが出たら、また次の質問を、というように、自由な発想、思いつきにそって、クリックやタップといった簡単な操作だけで、わかりやすい画面上の情報を探索できる」と話す。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する