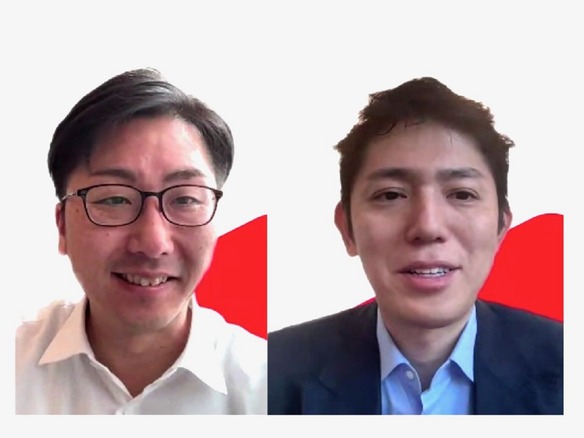
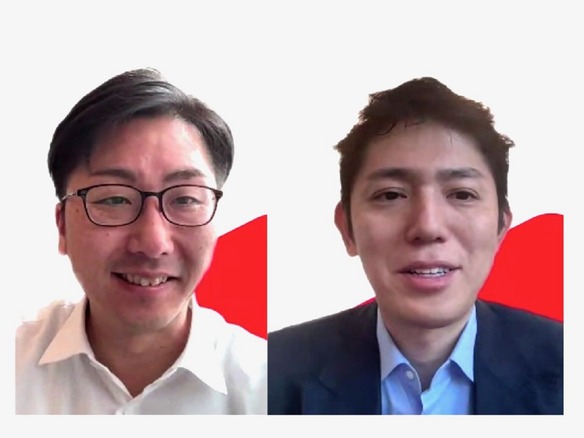
既報の通り、メルカリ子会社のメルペイは「メルカード」の名称でクレジットカードの提供を開始した。これまでにもメルカリのアカウント残高などを使ったプリペイド方式のバーチャルカードの提供を行っていたが、「クレジットカード」でかつ「物理カード」という形態は同社初となる。
このメルカードによるクレジットカード事業参入をはじめ、メルカリはいま「Fintech」と呼ばれる金融テクノロジーの世界でどのような将来図を描いているのか、メルカリ上級執行役員SVP of Japan Region(メルカリグループ日本事業責任者)兼メルコイン代表取締役CEOの青柳直樹氏とメルカリ執行役員CEO Fintech兼メルペイ代表取締役CEOの山本真人氏に最新事情を聞いた。


メルカード発表のタイミングは、ちょうどPayPayが「PayPayカード ゴールド」の提供計画を発表した直後であり、初報のタイミングで「○○Payの名称で(QR)コード決済サービスを提供する事業者が続々とクレカ事業に参入するトレンドに乗ったのでは?」と感じなくもなかった。
クレジット/デビットカード、電子マネー、コード決済の3種類の支払い手段を合わせたものを日本では「キャッシュレス決済」と呼んでいるが、経済産業省の資料によれば2021年の国内の最終消費支出に対するキャッシュレス決済比率は32.5%で、このうち約85%をクレジットカードが占めている。5年以上前の9割超の水準からいえば下がっているが、それでもなお日本における決済の主役はクレジットカードであることには変わりない。
コード決済事業者がクレカ事業を強化するもう1つの要因として「クレカを取り扱わないとニーズを取りこぼす」というものがあるが、「コード決済だけでは限界を感じたから」なのではないかという見方が出てくる。だが両氏はこの見方を否定しており、「クレカはあくまで支払い手段の1つであり、事業のコアは“与信”の部分にある」と述べている。
青柳氏:「私がメルペイの統括をしていたときからクレカの構想自体はすでに存在していたので、5年をかけてようやくこのタイミングで“順番に”出せたというのが実際です。参入という意味ではコード決済では単価の低いところから始めましたが、“与信”の経験とか熟練度が上がってきたなかで、最初は10-20万円の枠までしか自信をもって提供できなかったが、現在では50万円までは与信できるようになり、ようやく日常使いのクレカを出せる段階に達しました。ビジネス的にクレカを出したいというのはあっても、与信事業をどう育てるかというのがメルペイのコアにあり、そこを入り口にして出口を順番に増やしてきたというのが流れです」
クレカは長年対面決済やオンライン決済で使われてきた実績もあり、利用できる場所が多い点が魅力の1つとなる。この点はコード決済と比べての利点であり、「提供チャネル(出口)を増やす」というメルペイの初期構想に合致する。一方で、クレカにはもう1つ重要なポイントがあり、それは「決済単価が高い」という点だ。日本人の行動様式として単価の低い支払いにはクレカをあまり使わないが、支払いが一定額を超えるとクレカ利用が急増する。前者の穴を埋めるのがコード決済だとすれば、メルカードの提供はこれまでメルペイに欠けていた後者の穴を埋めるのが目的となる。
青柳氏「伸ばせる余地の期待値というのはあります。メルカリ内においても、ある程度高額の商品だとクレカの利用が多いというのは数字を見て感じていました。メルカリの外と中という話がありますが、まずはメルカリの中でメルカードを多く使っていただき、お客様からみて一定程度利用されるカードという位置付けになれば、自然とメルカリ外の利用も増えていく考え方です。ビジネス的には外でも中でも使っていただくのがいいのですが、まずはメルカリで使っていただくカードとして商品設計を行っています。コード決済でも使える場所を増やせば増やすほど利用が伸びる現象が見られましたので、メルカードにおいてもポイントがたまって有用だと判断いただければと考えています」
冒頭で触れたPayPayのクレカ事業強化について青柳氏に質問したところ、「“体験”という意味で納得した部分がある」とのコメントが返ってきた。メルペイのコア事業が「与信」という話があったが、同社が提供する後払いサービスの「メルペイスマート払い」と「メルカード」の与信枠は一体化しており、それを「メルカリ」という谷津のアプリを開いて管理できる。こうした仕組みはPayPayでも実装しているほか、「LINEがVisa LINE Payクレジットカードと融合し、ポイントとかもアプリ内で管理できているのを見ていたので、いわゆるWebサービスから来た会社がカードを手がけてこうした融合“体験”を提供するのが自然であり、トレンドだと感じた」(同氏)ということで、インターネット事業を基盤とするコード決済事業者がクレカ事業に進出するうえでの自然な流れというのが同氏の考えだ。
青柳氏:「これは日本での話ですが、(メルペイCEOの)山本は以前までAppleやSquareにいて北米の会社の動向を見ていたので、いまでいうBlock(Square)のCash Appとかの体験を肌で感じていたのです。Cash Appは送金アプリですが、クレカのみならずいろいろな体験がそこには融合されており、非常にシンプルで使いやすいものです。2018年や2019年には「スーパーアプリ」みたいな話もありましたが、われわれとしては「そちらの方向にはいきません」と申し上げていました。あくまでメルカリユーザーにとって使いやすい、そんな体験の提供を目指しています」
前述のように日本のキャッシュレスの大部分を占めるのがクレカだが、必ずしも充分なサービスを提供できているかというと難しいところだ。Apple Payの国内参入でようやく「即時発行」の仕組みが広がったように、従来の慣習に固着してなかなか新陳代謝を起こせていない部分も大きい。これは“普段使い”のアプリ、この場合では「メルカリ」アプリとの連携を強化することで使い勝手を向上し、さらに利用機会を拡大していくのがメルカードの戦略となる。ユーザー体験という点について、山本氏はどのような取り組みが内部で行われていたのかを説明する。
山本氏「クレカを提供するというのは、いままでのメルペイや後払いと全然違ったものを出すというわけではなく、これまで構築してきた与信の仕組みや銀行との接続部分とかがあって、支払いのチャネルの1つとして物理カードを用意しました。また提供にあたって2つ重要なポイントがあり、1つは顧客体験、2つめは与信の成熟度です。メルペイのスマート払いを利用する方にインタビューを行っていると、「クレカだと使い切れないのでこちら(スマート払い)に乗り換えた」という話が出てきます。クレカそのものは50-60年の歴史がありますが、単純な板のカードなので日々のインタラクション(相互通信)が発生しません。いくら使ったかが見えにくく、あとで請求が来て驚くという苦痛です。カードの話ではなく、“メルペイ”を出すときに一番議論していた点に、アプリ体験を基に提供される決済の必要性というのがあります。カードを使うとアプリ側を意識するのが弱いため、カードがない状態でコード決済やApple Payを使うことによって管理し、上限設定を行ったりする流れを作ることがまずありました」
山本氏「もう1つの与信の成熟度ですが、少し前に「与信枠が急に下がってしまった」という話がありました。このように与信の変動が大きいと、日常的に大きい買い物で使うのはなかなか難しいです。問題の認識はわれわれにもあり、これをある程度満足いただける水準に引き上げる必要がありました。(金融機関などに与信情報を提供する)CICとか属性型の与信は変動がありませんが、与信を持てる人と持てない人の差が埋まらない。AI与信をやる意義は、より多くの方にリアルタイムの情報の酒席としてお出しすることにあります。メルカリはメルペイ以前から後払いの仕組みを提供していましたが、当初は2万円からスタートしてデータを蓄積。データが揃い、いま50万円まできて、クレカに匹敵するだけの蓄積ができたわけです。加えて、与信枠が変に乱高下しないためのブラッシュアップをかなり行っており、一定の満足できるレベルまできたのがこのタイミングというわけです。もちろん50万円が今後も上限ではありませんし、よりお出しできるのであれば、実際に与信上限を自分で設定したり、紛失時の対応とか、アプリですべて管理できます」
「AI与信」と聞くとリスクを感じる人が少なからずいると想像するが、実際には基本となる情報は他のクレカと同様にCICを参照しているし、そのうえで設定できる枠を過去のメルカリでの取引履歴など蓄積したデータを参考に付与しているに過ぎない。もともと後払い系の「貸し倒れ率」は低かったと山本氏は付け加えるが、これを一定水準に抑え込みつつ、どこまで枠を広げられるかが今後の課題となる。
山本氏:「AffirmやKlarnaなど海外のBNPL事業者が「使ってもらったことによる与信」を行っていますが、アプローチ自体は似ています。データの難しいところは、過去の情報にしか基づいて行えない点で、例えば金利の変動やインフレなど不確定要素に対する未来が延長線上にないという部分にあります。われわれの特徴として、メルカリをセットで考えて「手元の商品を売って返済しますよ」といった支払い能力も評価する点が挙げられます。単純に与信枠を与えてリスクを抱えるのではなく、売りと買いという2つの行動を合わせて“与信”を構築するのです」
アプリを通した体験ということで、今後メルコインをはじめとした新機能がメルカリアプリに搭載されることになるが、「結果としてスーパーアプリみたいにはなる可能性はあるが、必然性を考えて何でもプッシュするようなものは避けたい」と山本氏は述べており、スーパーアプリのような仕組みはメルカリアプリの目指す方向性ではないと青柳氏と同じ考えを示す。それよりはむしろ、常時ポイント還元を含めた顧客がよりメルカードを含むメルペイを使いたくなるような仕組みを構築していきたいという考えだ。
メルカリの金融事業という視点からの将来像で興味深い話をするのは青柳氏だ。同氏は現在メルコイン事業を推進しており、来年2023年春には暗号資産の取引事業をスタートし、Bitcoinの取り扱いを開始する。世界的にこの業界は現在FTX破綻にともなう取引疑惑のただ中にあり、いわゆる冬の時代に突入している。日本国内でもCoincheckの流出事件以降、事業者の参入は停滞し、実質的にライバルが少ない中での参入になると同氏は説明する。なぜいまメルカリが「暗号資産」なのか疑問に思う部分が大きかったが、青柳氏は「信用創造」と「ブロックチェーンへの投資」の両面からその意義を説明する。
青柳氏:「金融事業において、われわれのメルカリようにある程度の体制をもったコマース事業者は少ないでしょう。モノの売り買いをするマーケットプレイスのような場所です。これとFintech事業の組み合わせがメルカリのユニークな点ですが、もっといろいろなタイプの価値が交換され、価値の移転を促せるような場所であっていいと思うのです。分かりやすいのが車で、まだ自動車ローンなどは手がけていませんが、貸金業自体のライセンスは持っています。メルカリで中古車の譲渡やそれにともなう移転の手続き、さらにそれを整えて担保価値を出しつつ自動車ローンとか、マーケットプレイスを拡張していくなかで、信用創造をクレカやスマホ以外にも広げていきます」
青柳氏:「マーケットプレイスに直接つながらない金融業は選んでいませんが、こうした背景がなければ暗号資産交換業には手をつけませんでした。NFTを取り扱ったのもそうした理由ですが、ブロックチェーン技術を取り込んでマーケットプレイスに使っていけるんじゃないかと。メルコインを始めるにあたり、何のために事業をやるのか。収益はもちろんだが、技術への投資とそこから得られる期待収益が大きいです。最初はBitcoinですが、他の暗号資産も扱っていきます。NFT自体もどのように管理し、オペレーションを作り上げ、メルカリに転用できるかの経験を積んで、どこかで合流させます。FLOWといブロックチェーンがありますが、いろいろなNFTを載せていき、それで取引を行っていきます。まだメルカリには乗っていませんが、将来的にどう対応させるのか、モノの取引をメルカリ外で、またデジタル資産をどう流通させられるのかを考えています。アート作品とかが分かりやすいですが、履歴の追跡や真贋鑑定など、それを理由にメルカリを使わない方に対するフォローになります。同じ文脈で、メルカリでの取引を安全にする保険であったり、車の車検履歴のデジタル化、そして自動車ローンと、マーケットプレイス事業者としてよりやりやすくなるのです」
こうした仕組みをすべて自前で用意するのか、あるいは他の事業者と組んで行うのかは分からないが、マーケットプレイスの拡張の過程に金融事業があるという前提でみると、メルカリの一連の戦略が見えてくるようになる。青柳氏はまた中長期的な展望として、特定パートナーとの協業で2次流通マーケットを構築できないかという考えを挙げる。メーカーが最初に消費者に商品を届けるのが1次流通とすれば、それがリサイクルなどの形で再販されるのが2次流通マーケットとなる。メルカリはまさにこの2次流通だが、その市場をパートナーシップで構築できないかという話だ。
青柳氏:「特定の電気製品でもいいのですが、最初に売った時点で会社によっては2次流通のマーケットを作ってしまおうというところがあります。そこにデュアルという形でリスティングしていただいてもいいのですが、結果的にわれわれが組めていないパートナーシップが広がり、より循環社会が実現できます。短期では難しいですが、将来的には1次流通や2次流通のみならずサプライチェーンにも入っていって、サーキュレーションチェーンをやるというのもあるでしょう。このような形で川上のプレイヤーとパートナーシップを結んだとき、われわれの付加価値は何かということになります。2次流通を安定させつつ、もともとの1次の価値も毀損せず、価格も壊さない。そこまでいければメルカリ自体のスケールも大きくなりますので、難しいですが手がけていきたいテーマではあります」
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する