

筆者は、情報技術や経営情報システム、情報倫理などを専攻しており、2022年3月で定年退職するまで、フェリス女学院大学国際交流学部で、丸27 年ほど専任教員を勤めて来た。
ちょっとした縁で、2014年に、ある地方自治体から一次産業のインターンシップ名目での現地実習の誘いを受けた。地方の過疎や一次産業などの衰退は、ニュースレベルの知識は持っていたが、実感としては把握していなかったこともあり、当時のゼミ学生6名と当地に足を踏み入れることとなった。その場所は、徳島県海部郡海陽町という高知県との県境にある、太平洋に面した比較的大きな自治体である。漁業インターンのチームは、大敷網という漁法で知られている鞆浦漁港が研修先だったが、農業チームは、同町大字九尾という集落に向かった。そこは、いわゆる限界集落である。最寄りの駅から、山道を自動車で1時間強ほど行った深い山に囲まれた地域で、住民数は当時20名に満たなかったと記憶している。筆者を含め、殆どのメンバーは、四国や徳島県には縁が無く、初めて行った場所が限界集落という、稀有な体験だっただろう。
写真は当時撮影した、集落の中心となる通りと集落唯一の商店の様子である。現在はストリートビューでも見ることが出来るが、佇まいは全く変わっていない。この蔭田商店は、鮎の干物などでも知られている。後述するが、この商店の建物が、この地域への疑問を解き明かす鍵ともなった。

当時の我々は、地方とはいえ所詮は同じ日本だろうと軽く考えていた。前職のフェリス女学院大学は横浜市にあり、学生の多くは関東圏の出身である。また地方出身者でも、地方都市に実家がある学生が大半だ。そのため地方の現状に関しては実感がなく、ましてや限界集落など、メディアで取り上げられるもの程度の印象しか持ち合わせていなかった。おそらく都市部生活者の大半は、そんなものだろう。たとえ祖父母が地方に在住していたとしても、それこそ盆と正月に顔を出す程度でしかなく、その土地以外には大して興味や関心を持ち合わせないというのが、実状ではないか。
徳島県海陽町は、過疎指定がなされている自治体である。その中の人里離れた集落である九尾は、限界集落とも呼ばれており、当初は自然の中にぽつんとある、高齢者しかいない覇気のない地域を想像していた。若い人たちも全く来ない、それこそ行政にも見放されたような、消滅を待つような………。
しかしその集落に学生達と足を踏み入れ、畑仕事を手伝い、集落の集会所で昼食を一緒に作り、山菜や鮎など、普段食べている食材とはまったく違う新鮮なものを食べながら、集落の高齢者たちと話していくと、当初考えた想像はあっという間に吹き飛んでしまった。自分たちが地方や過疎に対して抱いていたイメージが、いかに貧弱なものだったのかを、思い知ることになったわけだ。

大げさに言えば価値観の転換、それこそパラダイムチェンジであるが、端的に言えば、「限界集落」とは持続の限界が来た集落と言うことではなく、それまで生き残って来た、つまり生存能力が高い集落だったのだということである。例えば、集落九尾に行くためには、徳島県道301号線が唯一のルートだ。その街道沿いに、中山間部の集落である尾崎や芥附、小谷、広岡、角坂、船津、塩深といった、名前からして由縁がありそうな地域があり、そこを縫って九尾に至る。しかしその道路は、台風の季節などには倒木などで通行不能になり、陸の孤島になってしまうこともあるそうだが、九尾のおばあちゃん達に言わせれば、道路の補修などは少々ならば自力でやってしまうし、しばらく道路が使えなくても何の支障もなく暮らせるという。これを元気がない集落とは誰も呼ばないだろう。
漁業のインターンシップでは、漁師さんが実に生き生きと日々を過ごしているかを実感し、地方では確かに若者、特に女性が少ないという実態もよくわかった。学生たちは、どこに行っても大歓迎され、二言目には嫁に来いとの暖かい(笑)言葉をもらったのも確かだ。地方の実態を目の当たりにしたという意味では、海陽町には大変感謝しているが、我々には大きな疑問が残ることになった。
おそらく自治体側は、都市部の大学生がその地域のさまざまな産業や文化に素直に共感し、SNSなどで発信してくれることを期待したのだろう。それは別に海陽町だけではなく、筆者が研究室で実施した他の社会連携プロジェクトなどと本質的に変わることはない。しかしあえて言うが、そんなことがその地域にとって本当に必要なことなのだろうか。
なお、この時の学生たちの疑問や行動などは、徳島出身の映画監督である明石知之氏の眼に留まり、2019年に「波乗りオフィスへようこそ」というタイトルで映画化された。同監督はフェリス女学院大学に来校し、このインターンプロジェクトに参加した学生にインタビューをした。その時に学生たちが語った海陽町でのエピソードが、ほぼ実話としてその映画では描かれている。宮川一朗太氏演じる大学の教員が筆者であり、さらに海チーム、山チームの学生が何名か登場するが、それも実際のゼミ学生がモデルである。
数日間のインターンシップによって、現地の産業を都市部の学生たちが体感することにより、地方をどのように受け止めたか、それをその地方にフィードバックする報告会を開催して、プロジェクトは終了した。おそらく地方側としては、もっと違った成果が欲しかったのではないかと思うが、我々にとっては大きな発見だらけだった。
例えば漁業は日本のどこでも固有の文化を持ってはいるが、後継者不足や資源の枯渇など、産業としては様々な課題を抱えていることなどを体感することで、学生達には得難い学びになった。海陽町だけの話ではないだろうが、山間部の森林資源が生み出す養分が、地域内を流れる海部川を通り海に流れ出すことで豊かな漁場が作られていることなど、海と山の地域に分かれて足を運んだ学生らが相互に議論することで、一次産業の地域内連関がはっきりわかった。彼らは海陽町の印象を「一次産業の箱庭」と名付けて成果報告をしたが、おそらく地元側は「それがどうした?」と思えたんだろう。非常に微妙な反応だったのを記憶している。
実を言えば、我々には集落九尾にまつわる大きな疑問があった。幸い次年度も継続して同町からは依頼があったため、改めて前年度に参加した学生を含めて、集落に再訪することになった。
前述のように、同プロジェクトは漁業と農業という一次産業の就労体験を中心としたものである。集落九尾では、山間の斜面に張り付いたような石造りの棚田で、寒茶という固有のお茶と集落の中心にわずかに開墾された田畑によって、バターナッツをはじめとした蔬菜や米などを栽培している。そこで作業をしながら、参加二期目のある学生が、「なぜここが農業の町なんですか?」という疑問を口にした。確かに、この地に至るまでの平野部から中山間地域の方が、遥かに豊かな田畑が広がっていた。漁業はともかくとして、なぜこのような地域が農業の地域として認識されているのだろう。そもそも、この集落は農業をするために人々が集まって来た地域なのだろうか。しかし地域住民や行政の担当者に聞いても、どうも要領を得ない。大げさに言えば、この集落には何か大きな謎がある。そんな感想が残った。
映画には、限界集落に行ってインターンシップをした学生の、そんな疑問が描かれているシーンがある。その学生をモデルとした登場人物が、やはり当地の農業を営む高齢の女性に、限界化してしまったそんな集落になぜ暮らしているのかと尋ねるくだりだ。
同地のインターンシップは2期で終了したが、我々はどうしてもその謎が拭えず、結局自費でその後3回、計5回ほど、九尾という集落に、毎年のように足を運ぶこととなった、現地の役場の方に協力してもらいながら、地域の住民や元住人への聞き取り調査や文書館での文献調査など、徹底的に分析をした。
実は当初、その集落の方々は決して快く受け入れてくれたわけではなかった。その辺りも映画では描かれているが、どこかよそよそしく話しにくい印象はあった。しかし3期目に伺ったときには、間違いなく「またおいで」との言葉をもらったし、4期目にはやっとその地域のさまざまな過去のことを聴き出せた。それは決して隠していたわけではなく、そもそも我々の疑問がどういう意味なのか、おそらくはその疑問自体が伝わっていなかったということだった。
結論的に言えば、この町は決して農業の地域ではない。昭和40年代にこの地域を出た元住民の方に、数枚の写真を見せてもらった。そのうちの1枚を示す。それらは、地域を歩いたり、話を聞いたりした結果、おそらくこういった写真が残されているはずだと仮説付けた通りのものだった。なおこの写真の公開に関しては承諾済みである。
全てこの九尾と言う集落で写したものであり、おそらく昭和20年代後半から30年代にかけてのもので、最も古いものは戦前のものと推定される。残念ながら細かい撮影日時など、書誌情報などは失念してしまったそうではあるが、この集落がなぜ生まれたのか、どういう産業によって住民の方々が暮らしてきたのかを示す、貴重な写真である。

この写真が撮影されたのは、おそらく昭和20年代の後半から30年代の初頭とのことで、撮られた場所は、本文の最初に示した集落にある唯一の商店の前だ。特徴的な瓦屋根と木造の外壁がそのまま今に残っている。そのこと自体も驚きではあるが、建物の前で談笑する男性の横に、材木や板、樽などが見える。実はこの建物は、製材所だったそうである。つまりこの地域は、元々山仕事、すなわち林業のための地域で、近隣で伐採された木材や木炭などの集積地域だったということがわかった。実際に戦前に撮られたとおぼしき記念写真もあるが、そこには「九尾地区薪木組合」と描かれた看板が写っている。たくさんの若い人たちが写っており、当時は栄えた地域だったことが伺える。
戦前から高度成長期までは、木材は建材としても燃料としても貴重な資源だった。四国山脈はそうした木材資源の産地であり、九尾という集落も林業を中心に栄えた地域だったということである。実は周囲の山々にある豊かな森林も、杉を中心に、昭和20、30年代に植樹した樹木だそうである。 しかし戦後、エネルギー革命が進行し、さらに建材としての木材の需要も減り、安価な輸入木材によって国内の林業は衰退の一歩を辿ることになる。この集落でも、地域を去る人が増え、その結果として過疎、限界化を迎えた。それがこの集落の歴史ということなのだ。
限界化するまでに至らず、急激に人口が減って廃村になってしまった集落は数多くあり、関東圏では埼玉や秩父方面に非常に顕著にみられる。筆者の研究室が調査した結果であるが、それらの多くは石灰石など鉱業を中心とした地域であるケースが多い。石炭を代表とする鉱業を基幹産業とする地域は、閉山によって一挙に廃村にまで至ってしまう。しかし林業地域は、森林保全の作業などもあり、緩やかに人が減っていくことが多い。その上、林業人口を賄うために農産物を扱う機能も集落にあるため、結果として農業の地域としてのみ生き残ったというのが、この九尾という限界集落の実態だったのだ。
今ある限界集落の大半は、元々が林業の地域として成立して来た、かつては国の基幹産業の一端を担っていた地域の成れの果てということになる。そして、そこに至るまでに廃村になってしまった地域も数限りなく存在する。実際に九尾の先には、かつてもう一つ炭焼きを中心とした小さな集落があったそうである。しかしそういう証言も、この写真を見て初めて住民が語り始めたものなのだ。
その地域とどう接するか、まずは知らなければ何も始まらない。しかし、そもそも地域の人々が、その地域のことを全て理解しているわけではないし、忘れてしまっていることも多々ある。過疎化した地域や限界集落でも、最初からそうだったわけではない。まずは、地域を時間軸で見るという視点を持たねばならない。そして1枚の写真は人々の記憶を喚起し、新たな地域に対する観点を生み出すことになる。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ビジネスの推進には必須!
ビジネスの推進には必須!
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
 CES2024で示した未来
CES2024で示した未来
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
 「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む
「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む
 ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める
ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める
 「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望
「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望
 Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く
Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く
 3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは
3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは
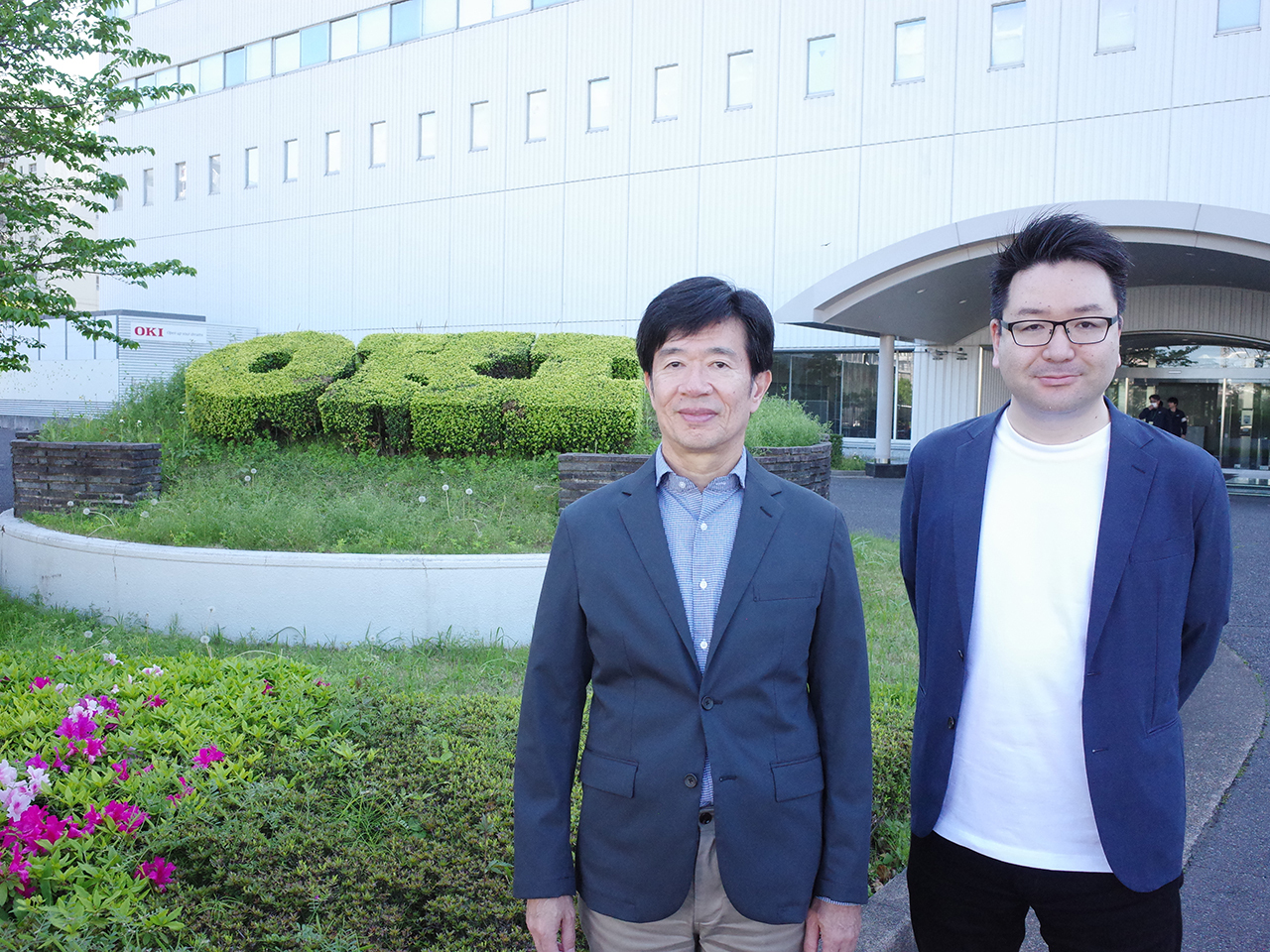 OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策
OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策
 中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ
中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ
 天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い
天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い
 Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く
Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く