

Linuxの大手ディストリビュータとして、パッケージ製品やサポートなどを提供するレッドハット。米国本社はエンタープライズ向けのサポートビジネスの確立で黒字化を達成。ディストリビュータが商売として成り立つことを実証した。今回は米国本社のヴァイスプレジデントで日本法人の代表取締役でもある平野氏に、ディストリビュータの役割や今後の課題について聞いた。
|
末松: まずは基本的なところから押さえさせてください。Linuxにおいてレッドハットが果たしているディストリビュータの役割とは何なんでしょうか。
平野: オープンソースは、文字通り星の数ほどウェブ上に公開されていますし、ユーザーはその中で自分の使いたいものを選んでダウンロードします。ただそれは手に入れられるだけであって、実際使用するには自分でコンパイルする必要があるし、動作が保証されているわけでもない。ですから使用中に何か問題が起こったとしても、サポートを頼めるところはありません。友達間のレベルで不明な点を聞くことはできるでしょうが、問題が解決するとは限りませんよね。
ウェブサーバ用のApacheやファイルサーバ用のSambaなど、用途が限られたアプリケーションは、ターゲットのイメージが決まっているし動作も安定していますので、プロフェッショナルな人たちはそれをうまく使って十分な成果を上げられてきました。だからこそ急速に普及したんですが、それ以上のこと──例えばデータベースを構築しようとした場合、PostgreSQLやMySQLなどのオープンソースを使うにしろオラクルを導入するにしろ、運営には別のノウハウも絡んできます。ですから我々のようなディストリビュータが市場のニーズに合わせ、数多くのオープンソースモジュールの中からひとつのサンプルとしてリストアップしたものを動作検証し、インストーラーと一緒にパッケージとして提供する、このことを一般的にはディストリビューションと呼んでいるわけです。
 |
|
レッドハットの場合は、約1500個のパッケージをオープンソースとしてFTPにアップしており、我々が有償でサポートすると宣言しています。内容はLinux OSと、いくつかの基本的なアプリケーションで、レッドハットでの動作チェックを終えてバージョンを固定したものです。ユーザーはFTPからダウンロードして無償で使え、依頼がない限りレッドハットはサポートしません。最初からサポートも含めた有償での利用を希望する場合は、我々がパッケージを顧客へCD-ROMで提供し、サポートも行っています。
末松: パッケージの動作保証やサポートなどのサービスがビジネスモデルだということですね。ソフトそのものに課金するということはあり得ますか。
平野: レッドハットの場合は、ありません。例えば店頭で売っている1万4800円のLinuxパッケージが売れたとしたら、そのうちの何割かは店舗や流通へ、残りがレッドハットの売り上げになる。それは30日間の問い合わせサポートなどのサービスへの対価としていただくものでライセンス料金としてではないのです。
末松: ディストリビュータはLinuxコミュニティに貢献しているということですが、社員のそういった貢献という業務を人事評価するのは難しいのではありませんか。
平野: オープンソース全般へ貢献する人たちは、別組織で扱っているんですよね。1998年の8月にレッドハットがナスダックへ上場した際、一緒に基金を作っており、そこから多少の報酬を渡し、自由にやってもらっています。
ビジネスと直接関連する「Red Hat Enterprise Linux」のような製品のメンテナンスをする人に対しては、レッドハット側が決めた給与を支払っています。レッドハット製品はLinuxのソースツリーとロードマップを共有しながら作っているため、Linuxコミュニティとオーバーラップする部分も多いのですが、今のところ特に混乱は生じていないようです。
末松: レッドハットはオープンソースのビジネスで、シェアを伸ばすことに成功してきたわけですが、その成功の鍵はどこにあると考えていますか。
平野: オープンソースビジネスとしては、システムインテグレーション、メンテナンスや運用管理、サポート……といったことが考えられますよね。しかし我々はRed Hat Enterprise Linuxというプラットフォームにきっちりフォーカスし、ある一定のレイヤーをサポートすると定義したことが大きかったと思います。
 | |
一般的にソフトウェアのサポートはレベル1〜3までの段階がありますが、レッドハットのメインビジネスは「レベル3のサポート」です。レベル1は、いわゆる「ファーストコール」。顧客からの電話を受け、「電源を入れてなくて動かない」といった初歩的なこともケアします。レベル2は、レベル1でも解決できなかった内容をチェックし、その問題がパッケージのバグかどうかを切り分ける作業のこと。バグでなければ「マニュアルのこの部分に書いてある」と提示したり、代替え案としてのソリューションを提供します。レベル3とは、生じた問題がバグであることを確認し、バグをフィクスする部分です。
レッドハットが直接サポートを請け負ったエンドユーザーに対してはレベル1、2も担当しますが、日本においてのレッドハットLinuxは、IBMや富士通、NEC、HP、日立製作所、Dellといったベンダー経由で出荷されるケースが多く、その場合のレベル1、2サポートは各メーカーが受け持ちます。
ディストリビュータの中にはアプリケーションやユーザー寄りの戦略をとるところもありますが、レッドハットはむしろ外す方向に動いてるんですよね。何もかも全部やるというのはオープンソース向けではない、階層ごとに分けて、みんなで協力して進めようというのが、オープンソースビジネスの特徴だと考えていますので。
末松: しかし、ビジネスの思想は、他社に顧客をとられないようクローズにして囲い込もうとするのが一般的です。オープンな思想を持ったLinuxの世界でも、ディストリビュータが改変を加えたものをいったんユーザーが使ってしまえば、同じディストリビュータと付き合い続けなければならない羽目になるのでは、という危惧もありますが、レッドハットは、その辺をどう考えているのでしょう。ユーザーがほかのディストリビュータを利用したい場合、簡単に乗り換えられるのですか?
平野: 変更先がわからなければ何とも言えませんが、少なくともレッドハットが提供するパッチはソースコードも含めてオープンな状態で提供するので、何を改変したのかがわかるはずです。我々が提供するパッチはLinuxコミュニティが承認しているもので、世界中のレッドハットディストリビューションでも同時に同じパッチを出しています。逆に、顧客側がニーズに合わせて改変したいと勝手に独自のパッチを当てたり改変した場合はサポートできないという立場を明確にしているんです。
末松: レッドハットは、ビジネスでもオープンソースの思想を尊重していると……。レッドハットは企業向けとして「オープンソース・アーキテクチャ」を発表しましたが、これは多様なオープンソースの世界で、自社のアーキテクチャを顧客に提供しようとしているという捉え方でいいでしょうか。
平野: そうですね。具体的には、システムコールと呼ばれるローレベルのAPIを、つまりOSに対するシステムコマンドを統一したいということです。これが狂えばライブラリやアプリケーションに影響するので、絶対にガッチリ決めなければならない。例えばUnixはPOSIX(Portable Operating System Interface)の標準仕様に準拠していますが、LinuxのローレベルなAPIは必ずしもPOSIXとイコールではなく、Linux独自のスタンダードなんです。世界標準ではないしわかりにくいという指摘もあったため、オープンソース・アーキテクチャを考案しました。しかし現段階では、ベンダーが用意しているドライバやハードウェア内部のアーキテクチャとの兼ね合いもあり、未だ開発段階といったところです。
末松: 先ほど聞いたビジネスモデルに従えば、Linuxにバグが発生するとレッドハットに仕事が来るという構造ですよね。オープンソース・アーキテクチャを提示することによりLinuxが安定すれば、バグは減少し、ビジネスも減るのではないですか。
平野: Linuxを使う上ではセキュリティの問題が絶えずつきまとうので、それを保証し続けなければなりません。その都度バグとしてフィクスしていったとしても、おそらく定常的に発生するでしょう。
 |
|
それ以外の機能的なバグも、ハードウェアが進歩する限りなくなりません。例えば今でも「SMPカーネルの問題」と言われるものが存在しますが、これは8CPUを搭載したマシン上やブレードサーバーをグリッドコンピューティングに活用するのにLinuxを使う場合、リニアに対応できないというバグを指しています。2、3年前の4CPUまではうまくいっていたんですが。こういった状況にも対応しようとLinuxコミュニティや我々は奮闘していますが、未だ治っていないのが現状です。CPUも64ビットになって今後は128ビットへと進化していくでしょうし、デバイスの進化に伴いドライバも新しくなる……といった具合なので、絶えずフォローアップしていかなければなりません。
末松: ベンダー各社は現在、OSDL(Open Source Development Laboratory)が公開しているLinuxアーキテクチャを使うという流れにもなっていますよね。それは今後、ディストリビューションを必要としない方向を目指しているということでしょうか。
平野: いや、単純に言うとスタンダードな感じを出したいのではないかと思っています。レッドハットだけに頼むとどうしても「レッドハットLinux」というイメージになってしまうので、中立的な立場のLinuxのスペックを出したい、それでOSDLのような形にした方が安心感があるということでしょう。
でも実は、Linuxコミュニティのロードマップと、OSDLが出しているロードマップには多少ズレがあるんです。特に、通信分野で使われる「キャリアグレードLinux」と、データ管理用の「データセンターLinux」の2つ。というのは、OSDLはビジネス寄りの考え方なので、企業が注目する機能が搭載されて動作を確認できればパッと公開してしまう。しかし、「まだ完全には出来上がっていない」というのが、Linuxコミュニティ側の主張なのです。例えば、いまOSDLが公開しているIPv6部分を含んだLinuxを全部実装してしまえばおそらく問題が起こるだろう、だから現在実装できる部分だけを公開しようとコミュニティは進めているというふうに、食い違いが生じているのですよね。
末松: オープンソースという思想は共有してはいるものの、やはりコミュニティー側のカルチャーとビジネスのカルチャーとがマージするときに、少々混乱しているといったところでしょうか。
平野: 混乱と言うよりも、利害が異なるのでしょうね。ただしOSDLの中にもコミュニティに貢献している人はもちろんいますから、やり方が若干違うだけで、どちらがいいという問題ではないと思っています。
末松: しかし、レッドハットがオープンソース・アーキテクチャとしてAPIの標準化を進め、OSDLなどからも流れが複数でてくれば、混乱の原因にもなりうると思うのですが。
平野: ええ、そうなんです。組み込みLinuxもその辺と関連した問題を抱えています。というのは、携帯電話端末のような非常に小さいハードウェアは特殊なマイクロチップが入っていますよね。そういったハード側で決められた機能を動かすためのドライバを企業側が独自に作っているところがほとんどです。要するに、特定のハードに依存した標準ではないドライバですから、それに対応したLinuxをLinuxコミュニティに提案してもパイが小さすぎて受け入れられません。また、組み込みOSでは必要不可欠であり、TRONで実現しているリアルタイム機能のレベルが現在のLinuxではおぼつかないということもあり、メーカーは自分たちの作ったものと置き換えた方がラクだと思ってしまう。
レッドハットはシングルソースツリーであるLinuxの流れを損ないたくないという立場なので、組み込みメーカーにはLinuxコミュニティの意向を汲んだ実装案を出すのですが、先方にとっては先に述べたようなドライバやリアルタイム機能などの細かい問題が噴出するため、「このソースを使ってくれ」と逆に指定されてしまいます。我々はコミュニティのロードマップに反することはしたくないというポリシーが先に立つので、引き受けられないんですよね。一方で、例えばモンタビスタのようなディストリビュータは比較的そういったことには寛容で、今後マージしていけばいいという考え方なので、とりあえずはベンダーの要求を一旦呑む方法をとっている。それでうまく話がまとまるために、組み込み系に強いディストリビュータとして認知されているのだと思います。
末松: レッドハットは長期的、モンタビスタは現実的な視点で物事を考えているということですね。レッドハットはエンタープライズの方に力を入れているイメージがありますが、組み込みOSはどれくらい重要視しているのですか。
平野: 組み込みのマーケットは大きいんですが、収益が少ないんです。というのは、FTP版をダウンロードして自分たちで改変して使うため、サポートを必要としないから。例えばNTTドコモの次世代FOMAにレッドハットLinuxを採用するという報道がありましたが、我々はサポートを頼まれてはいないのでまったく知りませんでした。Linuxを採用する側としては最も標準的なものをベースにしたい、そう考えたときに、動作チェックが済んだパッケージであるレッドハットLinuxのソースコードを基にポーティングを始めるんです。
 | |
末松: デバイスに合わせて改変を加えたら、それはレッドハットLinuxではなくなってしまうし、ひいてはLinuxコミュニティのソースツリーからもかけ離れることになりますよね。Linuxの活用方法やLinuxブランドの適用、つまりどこまでをLinuxと呼ぶかという点があやふやになってくるのではないですか。
平野: 厳密に言うと難しいです。でも現段階では自社でポーティングしたものに対して一方的にサポートを要求されたこともないし、コミュニティを無視してLinuxが分岐していく流れが出来上がっているわけでもない。いまはLinuxのマーケットが拡がりつつある段階なので、問題にはしていない状態です。モンタビスタのようなディストリビュータを経由しているところも、改変部分をきちんとフィードバックしているはずですし。
末松: 長期的なレッドハットと現実的なモンタビスタで、フィードバックの仕方にもポリシーの違いが現れているとすれば、そこでLinuxが2つに分かれる、というシナリオも考えられますが……。
平野: おっしゃるとおり、その可能性はないとも言えません。モンタビスタは組み込みベンダーから受けた要求をすぐにはLinuxコミュニティへフィードバックせず、自分たちで何年かは抱えていくわけですよね。例えば先ほど話に出たLinuxでのリアルタイム機能は、モンタビスタが松下やソニーと開発したものをCELF(CE Linuxフォーラム)内の数社でメンテナンスしているのです。今の段階ではLinuxコミュニティーとギャップがあったとしても、お互いに分岐しようというつもりはないから、早ければ3年後、遅ければ10年後ぐらいに何とかなるはずだ、と考えているのだと思います。
かといって、モンタビスタやCELFと仲違いしているわけではないのですよ。みな、Linuxコミュニティをベースに、必ず何らかのコミュニケーションをしていますから。ただ、ビジネスモデルは異なるということです。基本的に、「Linuxを分岐させたくない」「Linuxコミュニティのロードマップに出来るだけ沿っていきたい」という思いは、レッドハットはもちろん、OSDLやモンタビスタ、CELFの皆が共有しています。「じゃあどうやってGPLにしていこうか」「他者のコピーライトを侵害しないためには、どうすればいいか」といった話はよく一緒に議論しますしね。
末松: なるほど、わかりました。Linuxの枝分かれに関してはLinuxに携わる企業すべてが危機だと捉えているのですね。立場や利害の違いはあれど、共通のプラットフォームを作ることでLinux全体のパイを拡げるというオープンソースの発想は大事に育ててほしいですね。
ビジネス側は、即座に行動したいし、コミュニティ側は、資産であるソースツリーとロードマップを大事にしたい。ビジネスとコミュニティの利害の対立は、これに限らず、起きない方がおかしい。その狭間に長期間いた企業だからこその重みのある指摘であった。
しかし、Linuxコミュニティには、利害背反する膨大な問題を解決してきたという、これまでの実績の蓄積がある。それは、相違点を論理的に構造化し、全体最適の視点を全員がもって判断し合意することによりのみ可能となるものだろう。酒の杯を酌み交わすことによる、表層的な信頼関係に依存する軟弱な問題解決力とはレベルが違う。オープンソースの本質とは、真の合意形成にいたるための議論をする力であるということもできる。
2003年11月14日 末松千尋
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 CES2024で示した未来
CES2024で示した未来
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
 ビジネスの推進には必須!
ビジネスの推進には必須!
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
 「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む
「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む
 ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める
ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める
 「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望
「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望
 Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く
Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く
 3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは
3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは
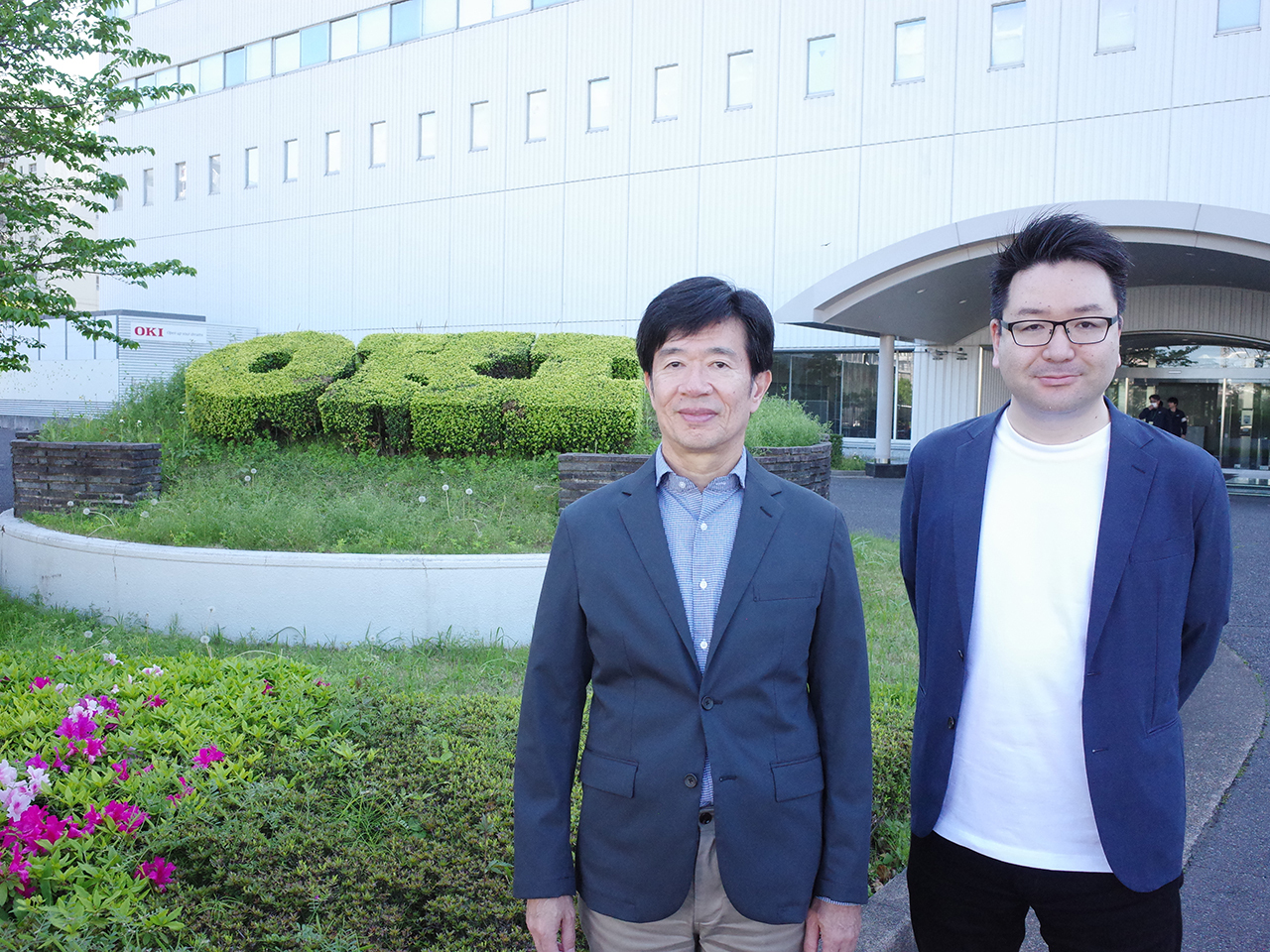 OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策
OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策
 中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ
中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ
 天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い
天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い
 Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く
Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く