

マダガスカルゴキブリ、英名マダガスカル・ヒッシング・コックローチは、人差し指ほどの長さの黒と茶色の無脊椎動物だ。「ヒッシング(シュッシュッと音を立てること)」という名が示すとおり、身の危険を感じると背中の穴から素早く空気を出し、「シュッシュッ」という音を出す。尻尾を立てて振ることで「ガラガラ」と音を出して威嚇するガラガラヘビを思わせる、奇妙だがクールな生物だ。

最近、そのマダガスカルゴキブリに関するニュースが飛び込んできた。科学者たちがこのゴキブリをサイボーグ化し、環境のモニタリングや、都市での自然災害発生時の捜索救助活動に役立てることを目指しているという。これもまた奇妙だがクールな試みだ。
9月5日、理化学研究所(理研)などの研究チームがゴキブリの行動を遠隔制御する仕組みを開発したことを学術誌「npj Flexible Electronics」で発表した。
この仕組みは、簡単に言えばゴキブリの神経系とつながれたバックパックだ。これを柔らかい超薄型の太陽電池と合わせてゴキブリに装着すると、ゴキブリの動きを妨げることなく、従来の約50倍の出力を達成できるという。ボタンを押すとバックパックに刺激が伝わり、ゴキブリを特定の方向に向かわせることができる。
そう気味悪がらずに説明を聞いてほしい。
ゴキブリのサイボーグ化は新しいアイデアではない。2012年にはノースカロライナ州立大学の研究者たちが、無線バックパックを使ってマダガスカルゴキブリを遠隔操作し、所定のルートを歩かせる実験を行った。
やり方はこうだ。バックパックと接続用のワイヤーを、ゴキブリの腹部の末端にある、「尾葉」と呼ばれる2本の感覚器官に取り付ける。左側に1つ、右側に1つだ。過去の研究から、左右どちらかに電気刺激を与えるとゴキブリはその方向に向かうため、移動をある程度制御できることが分かっている。
しかし信号を送受信するためには、バックパックに電力を供給しなければならない。通常の電池ではすぐに電池が切れ、サイボーグゴキブリは逃げ出してしまう。
そこで理研のチームが考案したのが、再充電が可能な太陽電池を使う仕組みだ。チームはまず、ゴキブリの胸部(体の上半分)にバッテリーと刺激モジュールを取り付けた。次の課題は、太陽電池モジュールをゴキブリの腹部(体の下半分)に確実に装着することだ。
人間はバックパックをうまく背負えるが、昆虫はそうはいかない。例えばゴキブリの腹部は分節化されているため、危機的状況になると体をねじったり、ひっくり返ったりする。粘着性のあるバックパックや充電池を貼り付ければ、ゴキブリは動きを制限され、体をうまく動かせなくなるだろう。
この問題を解決するために、理研の研究チームは薄型のフィルム電池を用いた実験を重ね、フィルムの厚さによってゴキブリの動作がどう変化するかを観察した。その結果、髪の毛の約17分の1の薄さのモジュールを使用すると、ゴキブリの自由度を大きく制限することなく、腹部に装着できることが分かった。しかも接着は1カ月後も維持された。これは従来のものよりも大幅に長い。
そして研究チームは実験を重ね、無線システムを用いてゴキブリの行動を制御できることを実証した。その様子は下の動画を見てほしい。実に興味深い。
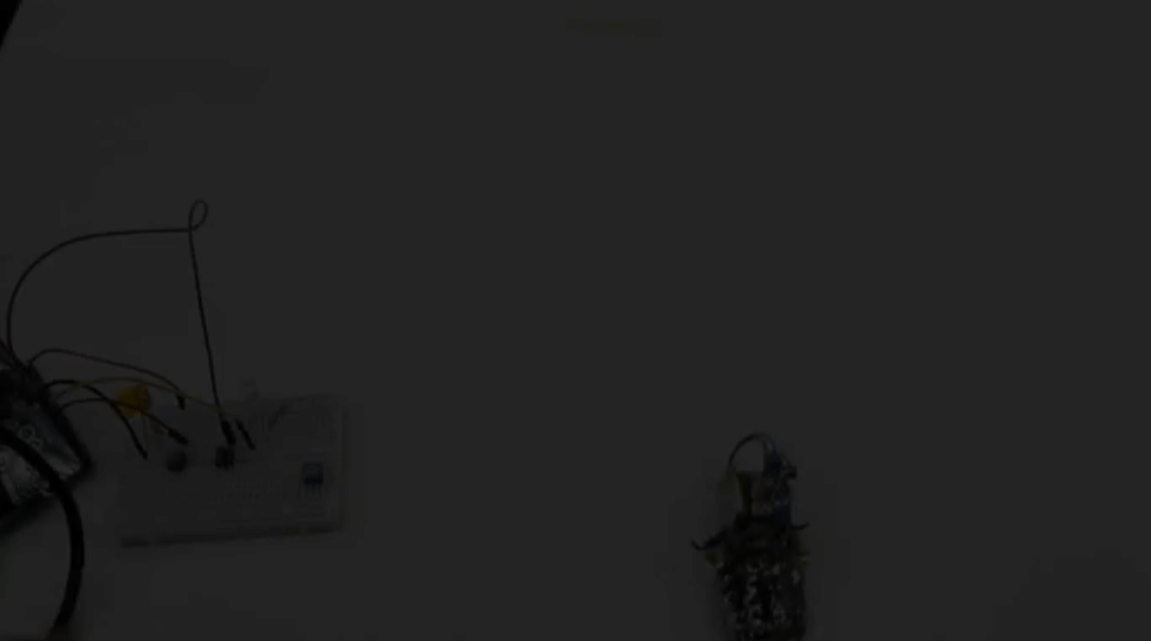
現在の成果はここまでだ。
フレキシブルエレクトロニクスの専門家である理研の福田憲二郎専任研究員は、「現在のシステムは無線を利用した運動制御システムであり、まだ都市型救助のような用途には応用できない」と言う。しかし「センサーやカメラなどの必要なデバイスを組み込むことで、そうした用途にサイボーグ昆虫を活用できる可能性がある」
福田氏によれば、カメラを動かすためには多くの電力が必要だが、現在の仕組みに組み込める、極めて消費電力の少ないセンサーは存在するという。ただしカメラを装着できたとしても高い解像度は期待できない。
超薄型太陽電池は、ゴキブリ以外の昆虫にも装着できると福田氏は言う。いずれは人間が制御する昆虫ロボットの飛行部隊が登場するかもしれない。候補となる昆虫はカブトムシやセミだ。
昆虫ロボットはちょっとしたブームになっている。7月には、米ライス大学の研究チームがクモの死骸を利用した「ネクロボット」を開発したと発表した。昆虫と機械のハイブリッドが生み出す、世界で最も不気味なクレーンマシーンだ。
しかし、ネクロボットに使用されるクモは死んでいるのに対して、理研のゴキブリは生きている。
正直に言うと、筆者はロボゴキブリが刺激を受けて特定の方向に進む映像を見たとき、ある種の罪悪感、または罪悪感に似たものを感じた。ゴキブリたちは、自分の脚が自らの意志に反して操られていることを理解しているのだろうか。苦痛を感じていないだろうか。「昆虫関連の研究によると、ゴキブリは痛みを感じない」と福田氏は言うが――。
近年、昆虫の感情に関する研究が行われ、昆虫を利用する研究がはらんでいる倫理的な問題も議論されている。Undark Magazineに最近掲載された記事も昆虫が感じる痛みについて取り上げており、昆虫の意識についてはまだ理解が進んでいないと指摘している。
この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 無限に広がる可能性
無限に広がる可能性
すべての業務を革新する
NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力
 川崎重工が目指す共創の在り方
川崎重工が目指す共創の在り方
「1→10」の事業化を支援する
イノベーション共創拠点の取り組みとは
 進化し続ける挑戦
進化し続ける挑戦
NTT Comのオープンイノベーション
「ExTorch」5年間の軌跡
 議事録作成もデジタル変革!
議事録作成もデジタル変革!
地味ながら負荷の高い議事録作成作業に衝撃
使って納得「自動議事録作成マシン」の実力
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する