社会行動が激変している今、従来の市場に最適化された企業活動はすでに時代遅れになっている。これが誰の目にも顕在化したのが、コロナ禍に突入したこの2年だろう。多くの企業がやっと危機感を持ち、デジタル・トランスフォーメーション(DX)という目標を立てて変革を推し進めている。
本記事では、この変革をいち早く実現したケースを紹介しながら、いま企業・経営者が持つべきビジョン、おこなうべきアクションについて解説する。今回、スタートアップから大企業まで、企業のDX・内製支援サービスを提供するゆめみの取締役である工藤元気氏と本村章氏の両名に話を聞いた。
工藤氏は、大手小売企業やメーカーのデジタルプロダクト開発のマネジメント支援に携わり、現在はゆめみの新サービス開発やマーケティング全般を担当。本村氏は業界を問わずさまざまな事業フェーズにおけるサービスデザインやクライアント企業のデザイン内製化支援に携わっている。
——激動の時期が続く中で、企業をとりまく環境の変化について教えて下さい。
工藤氏 : コロナ前は、国からDXを推進していくためのレポートが発信され、デジタル化を推進しようという空気が醸成されつつありました。そこでは、中長期でデジタルを自社の基幹事業に取り入れ、顧客とのタッチポイントを作り続けるためにデジタルの見極めができる能力を持つべきと記されています。
次に、コロナ禍に突入した緊急事態宣言後のDX推進状況をお話ししますと、ITRの調査結果(図1)を見ると、テレワーク制度の導入、リモートアクセス環境やコミュニケーションツールの導入はポイントが高い一方で、オンラインサービス事業の開始、販売チャネルのオンライン化といった消費者向けのデジタルサービスの推進に関しては、テレワークと比べると3分の1程度にとどまっています。
つまり、日本の企業はDXに対してもともと背中を押されていたのに、コロナになってもテレワーク導入が精一杯で、実際に生活者に対して利便性を提供するトランスフォーメーションはできていないのです。他に、国際的に見ても日本だけ明らかに低いというデータも出ています。
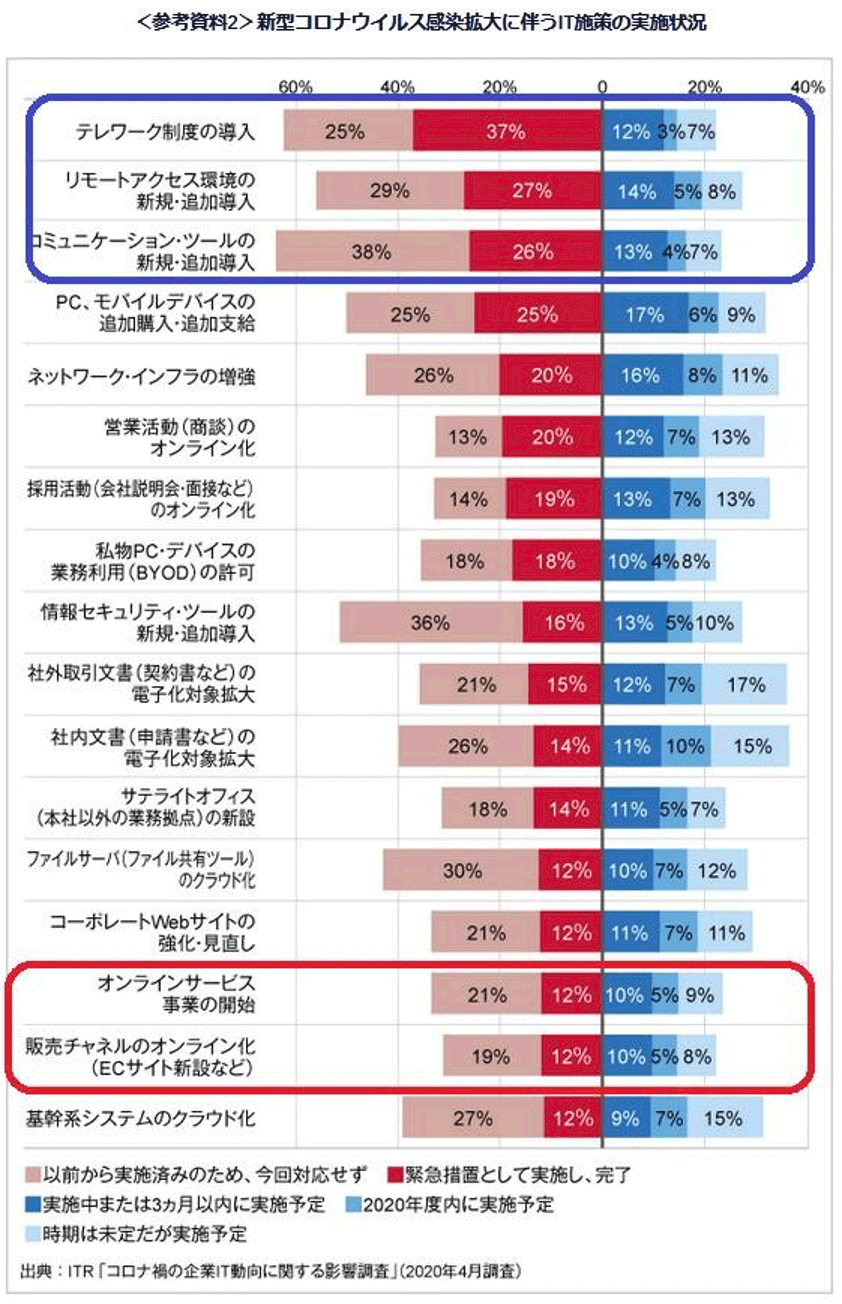
——働き方の部分では進んでいても、顧客の行動習慣を変えるまでは至っていないと。その上で、ゆめみが考えるDXの定義と、DXで目指すゴールとは何でしょうか。
工藤氏 : 私たちが見ている世界観を図解しますと、まず上にエンドユーザーがいて、スマホのタッチレス決済のようなデジタルサービスやプロダクトがあります。その下、裏側が企業の営みです。そこでは顧客向けのサービスと社内的な業務があり、社員やパートナーが各々の職域で動いています。
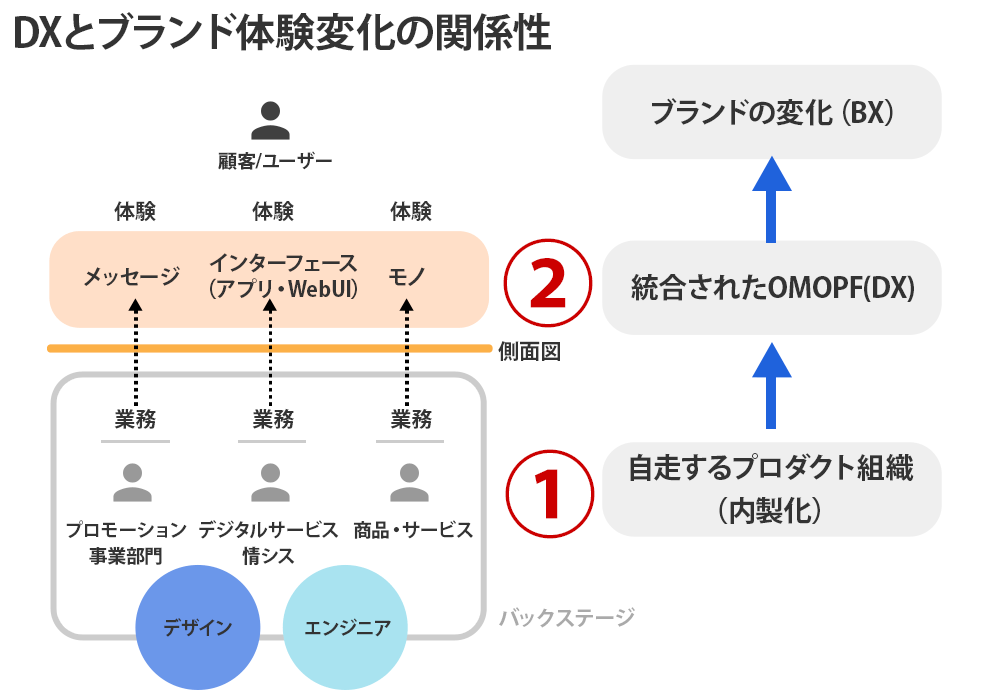
その中でDX化を見る際には、まず①のレイヤーで「デジタルに適応した業務ができる体制になっているか」がチェックポイントになります。これが私たちの提唱する「内製化」で、デジタルプロダクトを開発するために、どのパートナーやどのツールを使うという見極めができるようになる、つまり自走することがゴールとなります。
それが実現し、プロダクト組織でプロモーションとデジタルサービス・情報システム、商品・サービスの各部門が横串で価値観が共有できていると、②のレイヤーで提供される「モノ」やサービス、アプリやWebUIなどの「インターフェース」、あるいは、広告や「メッセージ」というそれぞれのユーザー体験にも一貫性が出てきます。その結果、企業目線でDXと思って取り組んできたことが、消費者にとってはOMO(Online Merges with Offline)プラットフォームが提供されている状態となり、かつそれをユーザーが使いこなせているようになっています。
その際に、企業がなぜそのデジタル化したサービスを顧客や社会に届けないといけないかという「メッセージ」が、うまく繋がった体験の連鎖として伝わることで、結果としてブランド体験そのものがAからBに変化する、つまりブランドのトランスフォーメーション(BX)に至るのです。
本村氏 : BXに至ったということは、DX通じて生み出された新しいブランド体験が顧客に届いているということです。デジタルを既存のビジネスに活用する場合は、①「既存の事業をデジタル技術を使ってサポートする」、②「既存の事業をデジタルに置き換える」、③「既存のオフラインも含め、デジタルで包み込んで全く違う新しい事業にしていく」――という3つの考え方があります。
それぞれでユーザー体験は異なってきますが、理想は③で、デジタルとオフラインを両方巻き込んでデジタルで事業を再構築すると、図2の体験やメッセージ、インターフェース、物理的なモノも必要になってくるし、それぞれのチャネルでちゃんとデータをやり取りしながら継続的にブラッシュアップしていけるような内製の体制も必要になってきます。そのような見方でDXを捉えていくと良いと考えています。
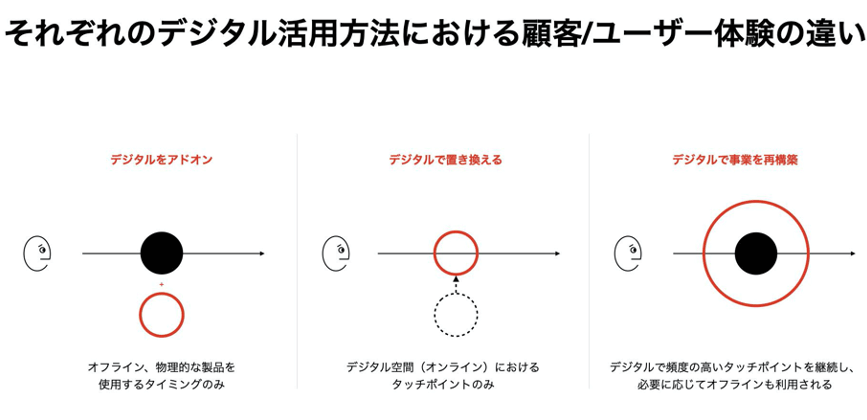
工藤氏 : 企業におけるDXのゴールは、各社でリソース、部門、製品の特徴、文化が異なるので、それぞれでゴールを描く必要があります。そしてDXを進めていく際のキーワードとして、アジャイル開発やクラウドサービスの活用という手法論が出てきます。たとえば今までは、ネットでビジネスをしている会社でも、大手のシステム開発会社にアプリやウェブサービスを発注して独自に開発していました。その際の時間をかけて要件定義をし、ウォーターフォールで開発するという形をトランスフォーメーションしていかないと、事業化のスピードで海外サービスや国内ベンチャーに後れを取ってしまいます。
「うちはネットサービスあるからいい」「ECをしているからDXができている」のではなく、競争性を持たせるにはさらに変化していかねばなりません。そういう意味でも、今の立ち位置に対してどういうゴールを敷いていくかが重要になってきます。
——背景には、消費者が新しいものに興味関心を抱くスピードに、企業が追い付けていないことがあると思います。その中で、DXがうまくいっている事例はありますか?
工藤氏 : コーセー様が、コロナ禍でブランド変革を実現された事例を紹介したいと思います。化粧品メーカーでは各社、高級ブランドをラインアップしていて、リピーターが付いたLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の高い主力商品群となっています。
以前の購入プロセスは、百貨店などの化粧品コーナーでビューティ コンサルタントの接客を受け、実際にその場で試してもらうなど対話をした結果、購買に至るという流れだったのですが、コロナになって顧客が店頭に行って買うという行為そのものの機会が減少してしまいました。感染防止の観点から、化粧品コーナーには自由に触れられるテスターが減ってしまい、商品そのものの色や質感を試せないことが起きてしまったわけです。
そこでデジタルの力を活用し、オフラインサービスのアップグレードを試みました。これまでもECサイトは存在しましたが、前述したように購買体験の成功要因は「品質の高い接客」です。一方でデジタルと言っても、わざわざ一つのブランドにアプリをインストールするなどは手間で、体験を損ないます。しかしながらコスメブランドだからこそ、接客時には肌の状態や化粧品独特の色や質感の見え方などなど、限りなくリアルに近い体験が求められる。そしてシームレスに商品が購買できるという消費者行動デザイン。こういった高いハードルに、ウェブの技術でアプローチしました。

ユーザーはアプリを入れなくてもウェブサービス上でビューティ コンサルタントの接客を予約して自宅から対話もでき、一方のビューティ コンサルタント側も専用のサービス拠点から「最近の肌はどうですか?」などと話をしながら接客して情報を取得し、販売提案のやり取りができるCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)型の接客ウェブアプリを構築したのです。今までもCRMはありましたが、タッチポイントをお店の接客体験から、タブレットやスマートフォンに置き換えたという形です。
コーセー様は、コロナ禍で生じた課題に対して、商品の特性や消費者の行動属性に併せてITの必要条件を引き上げるというDXを達成されました。ここで重要なのは、自社のIT部門がパートナーと一緒に、アイデアを出しながらプロダクトを作って実現し、その結果BXを達成したということです。感染対策という点では、消費者も安全だし、ビューティーコンサルタントもリモートで接客できるので安心で仕事がしやすくなっているという点でも、まさしくDXの成功事例といえます。
——そのほかに、事例から得られたDXを成功させるためのポイントはありますか?
工藤氏 : コーセー様では、リーダーシップを取られていたIT部門の方が、「要求が降ってくるのを待っているのではだめだ」と自ら掲げられていました。そういう覚悟が決まった人がいるかどうかは重要です。そのような方がいない場合は、ミッションをひとりで抱え込まないような、共有できるような組織を内製でチームビルディングすること大事になります。
本村氏 : 別案件ですが、自分たちでサービスのデザインを考え、機能の要求をまとめていくプロセスにおいては、内製で主導していく部署や役割を担う方が必要だと実感しました。そこは、これからDXを推進しようとしている大企業の共通の課題になってくると思います。
——ゆめみとして考える今後の企業活動におけるデジタルとの関係性について、今後どうしていくべきかをお話し下さい。
本村氏 : ゆめみでは、デジタル化を進めるにあたって「サービスデザイン」のプロセスを重視しています。経済産業省がDXについて、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して顧客や社内のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。その中の“顧客や社内のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革”という部分が、まさにデザインに相当します。
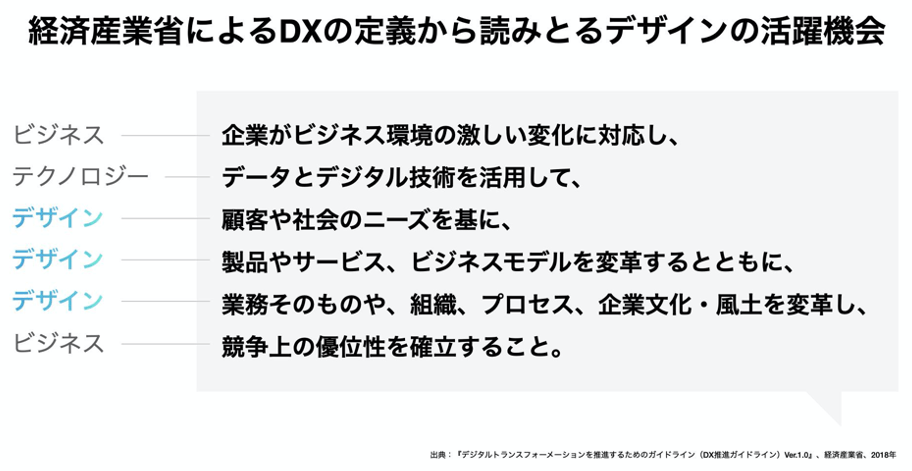
まずは、自社が提供しているサービスとユーザーニーズにどの程度ギャップがあるのか気付く必要があると考えています。実際、これまで私たちがご支援したクライアント企業の中には自社サービスを改善していく際に、ユーザーの声を直接聞くという取り組みをされたことがないことも多くありました。そこで当社が支援するプロジェクトでは、ユーザーがサービスを使っている様子を実際に見てもらう、またはユーザーから意見をもらうというプロセスを取り入れています。するとお客様は、これまでの先入観を取り払うようなユーザーに対する深い理解と気付きを得られます。このように、デザインという活動を企画のプロセスに取り込んでいくことは変革のための大きな一歩になります。
また、デザインの過程では私たちがすべて提案するのではなくて、一緒に考えてもらうようにしています。それによって、少しずつ自分たちの日々の事業における重要な活動の1つとしてインストールしていただくことができます。結果として、ITビジネスの課題が見えた時に解決をベンダーに丸投げするのではなく、自らが動いて継続的に課題発見と改善をしていけるような、アジャイルやスクラムでいうところの継続的なディスカバリーとデリバリーの体制を築いていくことに繋がります。
それができるようになると、デジタル時代のシステム開発やプロダクト開発との親和性が高い内製デザインの仕組み作りができるようになると考えます。
——数年前からコト消費が重視されるようになりましたが、それが実際にできているメーカーが少ないのはデザインの視点が欠けているせいかもしれません。その他に変革や改革で必要な要素は?
工藤氏 : コロナ禍でSlackなどのデジタルプラットフォームが普及し、企業間のコミュニケーションが変化しました。事業会社とパートナーの関係性が変わり、境界線が曖昧になってお互い価値を提供し、勉強し合っているような関係性が築きやすくなりました。それによって人間対人間の関係性が強まり、会社の壁が取り払われつつあります。これは継続すべきです。そのために当社では、ワークショップや壁打ちを推奨しています。
本村氏 : 関係性が変わることによって、私たちがプロジェクトをご一緒する際に、役職を意識せずにその場に参加している皆様と意思決定をしていく、意思決定のレイヤーがどんどんフラット化されていくのです。
そうすることで、参加している皆さんが納得した状態でプロジェクトを進められるし、効果の検証や測定もしやすくなります。

そう言いつつも大企業では、私たちが携わるプロジェクトが、社内に及ぼす影響範囲がそこまでの大きくない可能性ももちろんあります。したがって、ご発注をいただくご担当者の方としても、支援をする側である私たち自身もどの意思決定レイヤーにおけるプロジェクトなのかということは、常に意識しなければなりません。それを踏まえて意思決定のフラット化の両方を行いながら、まずは担当プロジェクトのスコープでできることから始めつつ、近接しているレイヤーとつなげていくことでより大きな組織変革を起こす支援をおこなっています。
工藤氏 : 以前は進められるがままに意思決定をされる方が多かったのですが、最近は「自分たちはこうしたいのだけど、どうロジックを足せるか」という壁打ち的な相談や、「自分事で進めたいのでアドバイスが欲しい」というお客様とのコミュニケーションが増えました。そこが、今回のテーマの1つである内製化を進めるにあたり、まさに意識の主体が移っている瞬間だと思います。そのような状況だからこそ、私たちもより高い専門性を発揮することができるようになっていると感じています。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する