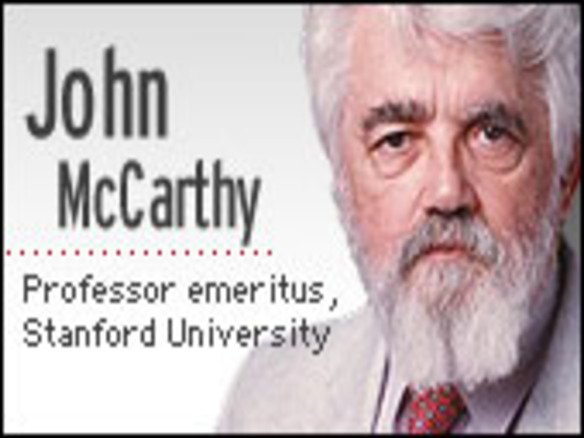
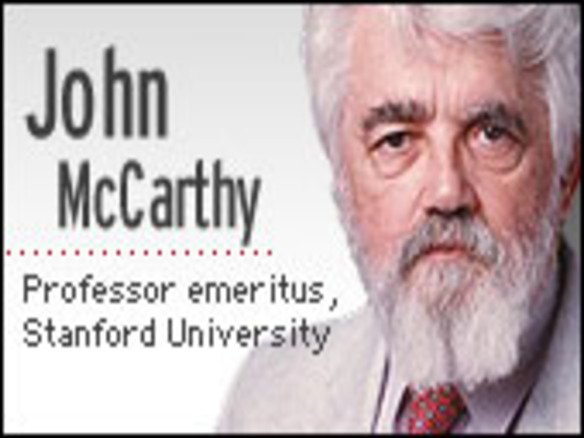
1956年、コンピュータ科学者のグループがダートマス大学に集まり、当時としては新しいトピックについて議論をかわした。そのトピックとは「人工知能」である。
ニューハンプシャー州ハノーバーで開催されたこのカンファレンスは、コンピュータで人間の認知能力をシミュレートする方法に関する、その後の議論の出発点となった。カンファレンスでは、「コンピュータは言語を使用できるか」「コンピュータは学習できるか」「創造的な思索と非創造的だが有効な思索を分ける要因はランダムさ(偶発性)なのか」といったさまざまな議論が行われた。
議論は、学習能力をはじめとする人間の知能が、原則として、コンピュータのプログラムでシミュレートできるくらい詳細に記述することができるというの大前提のもとで行われた。
出席者には、当時ハーバード大学に籍を置いていたMarvin Minsky氏、ベル研究所のClaude Shannon氏、IBMのNathaniel Rochester氏、ダートマス大学のJohn McCarthy氏などの有名な学者が名を連ねていた。
この研究分野は「人工知能」と呼ばれているが、この名前は、実はMcCarthy氏がこのカンファレンスの直前に考え出したものだ。今月、ダートマス大学で開催された50回目の同カンファレンスで、現在スタンフォード大学名誉教授のMcCarthy氏に、初期のAI、50年間の研究成果、今後の課題について聞いた。
ロックフェラー財団からカンファレンスを開くための研究資金を得るために提案書を書く必要があったのですが、そのときに思いついたのが人工知能という呼び名だったのです。実をいうと、こういう名前にしたのは、資金提供者ではなくカンファレンスの参加者のことを考えていたからなのですが。Claude Shannonと私で『オートマトン研究(原題:Automata Studies)』という本を書いたのですが、カンファレンスに提出された論文の中で人工知能をテーマにしているものが少ないと感じたので、何のカンファレンスなのか明確に打ち出すためにインパクトのある名前を考えてみようと思ったのです。
「計算知能(Computational Intelligence)」という名前に変更したがっている人もいますね。しかし、1955年当時に、この名前を使うことはできなかっただろうと思います。というのは、コンピュータがAIを実現する主な道具になるという考え方は、当時はまだ、ごく一部でしか受け入れられていませんでしたから。ですから、計算知能という呼び名を受け入れる人も少数派だったでしょうね。
スキルという問題ではなく、ハードウェアを活かすための基本的なアイデアがなかったということです。その点は今でも変わっていません。そのことは、コンピュータにチェスと囲碁を同じくらい学習をさせると、チェスはかなり巧くなるけれど、囲碁は全然巧くならないという事実によく現れています。囲碁では、局面、陣地を考慮しなければなりませんし、何より、囲碁の"手"を識別する必要があります。こうしたことは、コンピュータ上でどのように表現すればよいのか未だに分かっていないのです。
私の場合はそう、楽観的過ぎました。しかし、当時、かなり悲観的な考えの人たちもいたと記憶しています。
要するに、こういうことです。人間は自分の認識している障害しか考慮できない。昔より今のほうが認識している障害は多い。だから今のほうが悲観的な人が多くなってきたのでしょう。
そうですね。1つは、(人工知能を実現するには)コンピュータに「非単調推論」を実行させる必要があるということを認識したことでしょうか。
いいですよ。例えば、あるステートメントPがあり、これが複数のステートメントの集合Aから推論可能であるとします。また、別のステートメントの集合Bがあり、BにはAに含まれるすべてのステートメントが含まれているとします。通常の論理的な推論では、ステートメントPはBからも推論可能です。なぜなら、同じ証明が成り立つからです。ところが、人間はそうならないような推論をするのです。たとえば、私が、「ああ、11時には家にいるけれど、君の電話には出られないよ」と言ったとします。最初の「11時には家にいる」という部分から、あなたは「家にいるなら電話に出ることができるはずだ」と結論づけるでしょう。しかし、その後の文を付け加えると、そういう結論を引き出すことができなくなる。つまり、「非単調推論」というのは、ある結論を引き出したとき、それが正しい結論に思えても、何か別の事実が追加されたために、その正しさが保証されなくなる、そういう推論を指します。非単調推論が定式化され始めたのは1980年か、もう少し前くらいからですが、今では非常に大きな研究分野になっています。
われわれはまだ、人間と同レベルの知能を実現していません。でも、自動車を128マイル運転できるまでになったことは大変な進歩だと思います(編集者注:2005年秋のDARPA Grand Challenge で優勝したスタンフォード大学のロボットカー"Stanley"は、モハーベ砂漠で131.6マイルの自動走行に成功した)。
コンテクストを考慮した常識と推論の定式化をさらに進歩させていきたいですね。これは私が長年に渡って取り組んできたテーマであり、私以外にも取り組んでいる人が何人かいます。この研究はDARPAも支援しているのですが、アイデアが不足していて人間の知能に到達するレベルには至っていません。
そうです。それが私の考え方です。もちろん、人間の知能をシミュレートすることに興味を持っている人もいます。この考え方はいろいろな面で最善とは言えないのですが、Allen NewellやHerbert Simonなどが、そのような考え方をしていましたね。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 ひとごとではない生成AIの衝撃
ひとごとではない生成AIの衝撃
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
 プライバシーを守って空間を変える
プライバシーを守って空間を変える
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは
 心と体をたった1分で見える化
心と体をたった1分で見える化
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
 メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】
 なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは
 AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は
 パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生
 野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは
 「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に
 「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調
 物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは
 「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた
 培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり
 過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ
 通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く
 「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する
「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する