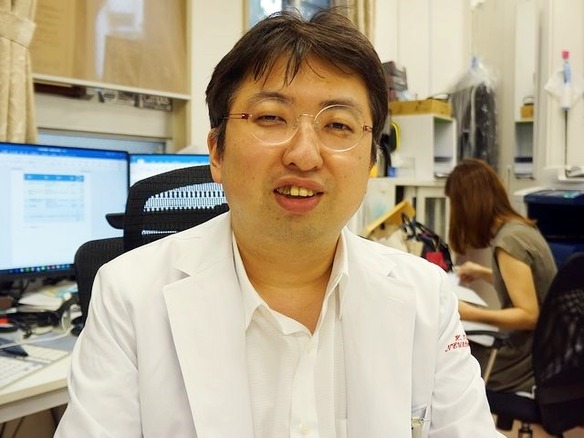
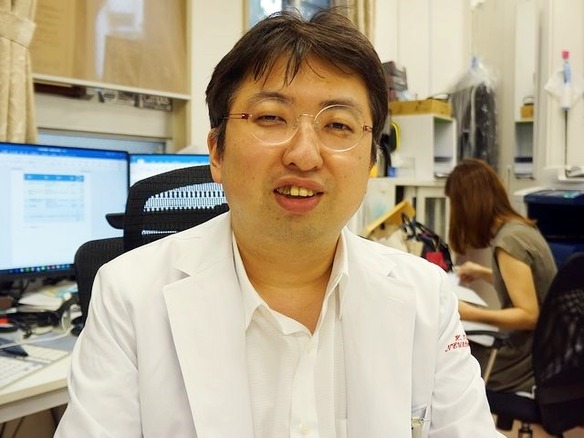
さらに、スマートフォンの次なるデバイスとして、大きな期待が寄せられているウェアラブル端末を始めとしたIoTの活用も見据えていると髙尾氏は話す。高齢化社会が加速することで、今後は在宅医療も増えていくことが予想されるが、たとえば患者が時計型のデバイスを身につけて日常生活を送ることで、常に血圧などの身体データを自動収集・送信し、それらのデータから医師が事前に病気を見つけ出すといったことが可能になるかもしれない。
また、突然倒れたり、救急車で運ばれたりするといった緊急事態においても、大型のCTなどで検査する前に、身体データを送ることで診断に役立てられると考えられている。端末にGPSが搭載されていれば、認知症の患者が行方不明になった際の捜索などにも活躍するだろう。慈恵医大では、すでに時計型のデバイスの開発を進めており、2017年度には院内に導入したいとしている。
こうした取り組みの先にあるのが、医師と患者の関係の変化だ。髙尾氏は、「本来は患者と医師が直接話せる環境が望ましいが、現在は医療法上それが認められていない。そのため、まずは身体データのデジタル化によって医師がすぐに病状を把握できたり、呼び出しシステムが発達したりすることで、医師と患者の関係が良好になっていく。その次のステップがホームドクター制などの世界だと思っている」と語る。
しかし、現実として医療業界はまだまだ紙に依存している側面が多いほか、たとえば電子カルテひとつとっても、費用が高い、新たな機器のスペースが確保できないという理由から、すぐに導入できない病院も少なくないそうだ。また、当初は国からの補助があったが、徐々にその金額が減っていくといった問題も起きていると髙尾氏は指摘。医療ICTの発展には、ICTを使った際には診療報酬をつけるなどの見直しを始め、国の支援が不可欠だと訴える。
このような現状がある一方で、慈恵医大の取り組みを知り、複数の病院からスマートフォンを導入する際の規約や問題点などについての問い合わせがあるといった、ポジティブな動きも起きているという。慈恵医大のような医療機関や大学病院が増えていけば、行政や国民の意識も変わり、日本の医療ICTをとりまく環境も少しずつ前に進むことだろう。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
 CES2024で示した未来
CES2024で示した未来
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
 データ統合のススメ
データ統合のススメ
OMO戦略や小売DXの実現へ
顧客満足度を高めるデータ活用5つの打ち手
 ビジネスの推進には必須!
ビジネスの推進には必須!
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
 誰でも、かんたん3D空間作成
誰でも、かんたん3D空間作成
企業や自治体、教育機関で再び注目を集める
身近なメタバース活用を実現する